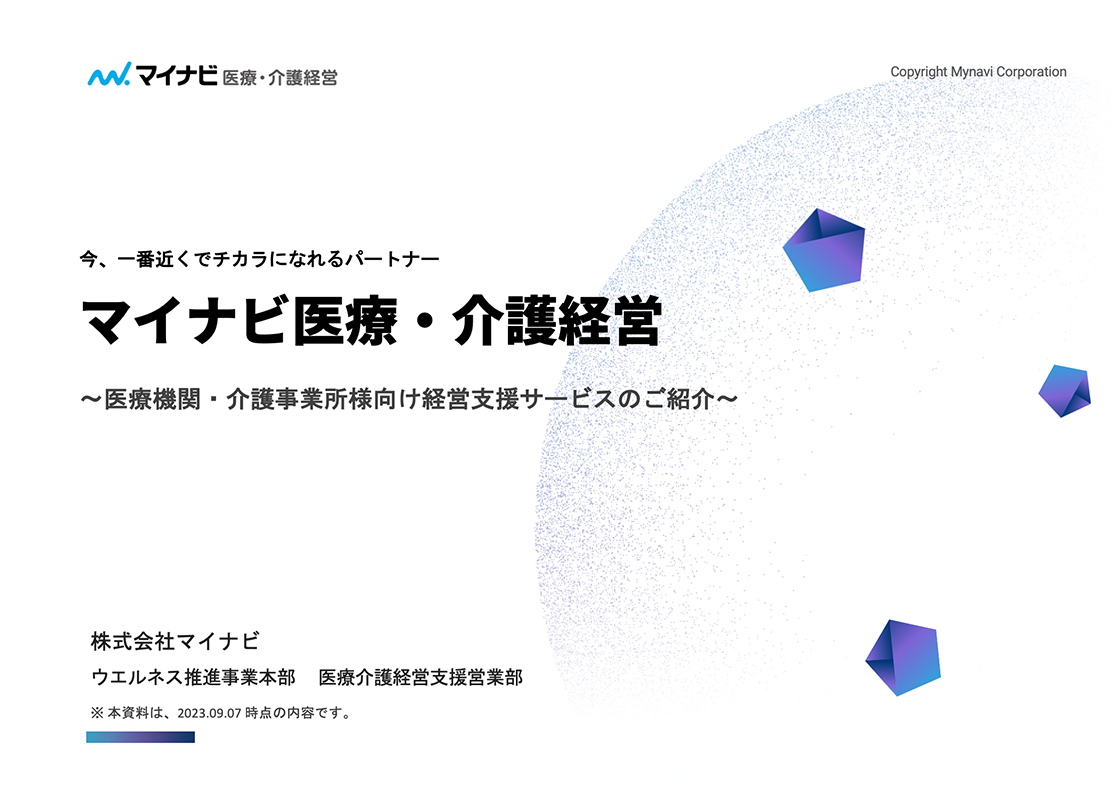このような課題を解決したい方へ
- 医療DXによる業務サポートで看護師の負担を軽減したい
- 導入に向けて第三者による客観的な意見が欲しい
- 深刻化する人材不足の課題を解決したい

日本の医療現場でも導入が進むDXーー医療DX推進
マイナビ医療・介護経営の専門家: 関西エリアの急性期病院で活躍している看護部長 S 氏
医療DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、医療の現場でデジタル技術を活用して、業務の効率化や患者サービスの質向上をめざす取り組みです。電子カルテ、遠隔診療、ロボット手術など、すでに導入を進めている医療機関もありますが、これから導入しようとしていたり、導入するかどうか悩んでいたりする現場も依然として多く存在します。関西エリアの急性期病院で看護部長として活躍するS顧問に、医療現場におけるDXの必要性や導入事例、外部顧問を依頼するメリットなどについてお話を伺いました。

看護と最先端技術を組み合わせることの必要性
少子高齢化の荒波を乗り越え、よりよい医療サービスを提供する上で、医療DXを活用した「新しい看護」がスタンダードになることを確信しています。今後、医療需要がますます増加する一方で、医療従事者の人材不足は深刻化する見込みであり、現行の医療提供体制を維持することが難しくなっていくでしょう。この課題を解決するために、医療DXは極めて重要な役割を担っています。
例えば、AIやロボットによる業務サポートは看護師の負担を軽減し、より質の高い看護を提供する新しいアプローチだと言えます。ただし、これは「人の温もりがない看護」というわけではありません。看護と最先端技術を組み合わせることで、看護師が本来の使命に集中できる環境をつくる戦略です。患者さんへの心のこもったケアや温かい言葉かけは、AIやロボットにはできません。一部の可能な業務をデジタル技術に任せることで、看護師は本質的な役割を全うすることができるのです。
医療現場におけるDX活用事例3選

しかし、一口に医療DXと言っても、具体的な活用イメージが浮かばないという方も多いでしょう。ここで、医療現場でAIやロボットが活躍できる事例を3つご紹介します。
- AIを活用した患者対応
インターフォンの機能を向上させることで、患者さんへの安心・安全な医療提供を維持しつつ、看護師が心理的な安全性を保ちながら効率的に働く環境を整えることができます。例えば、インターフォンにカメラ機能や音声認識機能を付けることで、看護師はナースステーションにいながら患者さんの状態や言葉をはっきりと確認しながら、迅速かつ効果的な対応が可能になります。
さらに今後、AIが組み込まれるようになれば、患者さんからの一般的な問い合わせに対して自動応答が可能に。薬剤や検査の説明など、よくある質問には問題なく対応できるので、看護師はより重要な業務に集中でき、患者さんの対応にも余裕が生まれます。さらに、看護師が「○○(疾患名)の観察ポイントは?」と尋ねれば、AIによる瞬時かつ正確な情報提供が看護師の判断をサポートし、業務の精度が上がることも期待できるでしょう。薬剤名や投与量などをAIとダブルチェックできれば、誤薬や投薬忘れを防止することにもつながります。
- ロボットによる医療物資の運搬
薬剤や輸血・点滴資材といった医療提供に必要な物資を運ぶ作業だけでも、毎日相当な労力がかかります。現在、こうした作業は主に看護助手などが手作業で行っていますが、これをロボットが代替する取り組みが進んでおり、実際にいくつかの医療機関で運用が始まっています。
ただし、ロボットが院内を自由に移動できるようにするには、いくつかの課題をクリアする必要があります。その一つが、動線の確保です。エレベーターに乗ったり、自動ドアを通過したりすることは可能ですが、取っ手のある扉を開けて進むことは現時点の技術では難しいため、自走できる動線を考えなくてはなりません。もちろん、患者さんにぶつからないよう、安全面を確保することも重要です。ロボットの自走ルートを試行錯誤しながら設計し、患者さんの妨げにならないようバックヤードで試運転を行い、私自身も運用に向けた支援に参画してきました。
- ロボットによる院内清掃
患者さんがいない診療時間外などに、「お掃除ロボット」が清掃を担うことで、職員の業務負担を軽減でき、また高レベルな清潔度が求められる場所では、紫外線消毒を取り入れる医療機関もあります(人体への影響を避けるため、夜間の外来や稼働していない手術室などで実施)。清潔な環境を維持しながら、職員の労力を削減するための有効な施策の一つです。
看護師から特に好評だった機器の導入事例
DXというと非常に高度な機器がイメージされがちですが、幅広く「職員の業務改善に寄与するもの」と捉えて、気軽に取り組めるところからスタートする意識も大切です。例えば、私が勤める急性期病院では、ディスポーザブルパルプ粉砕機を導入したところ、看護師たちから非常に好評でした。この機器は、再生紙でできたディスポのパルプ容器を汚物ごと粉砕し、排水処理を行うための装置で、汚物処理の業務効率化に役立つ機器。センサーを用いたハンズフリー方式である点が特徴です。
導入する前の当院では、使用済みの尿器や便器は、専用の機械で洗浄・消毒・乾燥して再利用していました。しかし、各病棟で1日に何度も発生するこの作業は、看護師たちの業務時間を地味に奪っていき、特に人手が少ない深夜帯で大きな負担になっていました。しかし、この製品の導入により、使用済みの容器を機械に「入れるだけ」で作業が完了するように。業務負担が大幅に軽減して効率化につながったことはもちろん、感染予防にも貢献してくれています。
DX導入において外部顧問から得られるメリット

いざ自院にDXを取り入れようと思っても、何から手を付けたらいいか悩んでしまうかもしれません。そこで活用したいのが、外部顧問です。依頼によりどのようなメリットが得られるか、3つのポイントをご紹介します。
- 組織外の第三者による客観的な意見
多くの病院には、良くも悪くも「独自のルール」が存在します。そのルールが職員の帰属意識を高め、チームワークの促進や院内の活性化につながっていればいいのですが、マイナスの方向に働いてしまうことも珍しくありません。長年、同じ組織に属しているとそれに染まってしまい、新しい視点に気付けなくなる可能性があります。しかし、第三者である外部顧問なら、そうしたルールに縛られず客観的な指摘ができます。また、院内の職員同士では立場や年齢による遠慮が生じがちですが、外部顧問の意見であれば誰もが意見を受け入れやすく、DXに関しても有益なヒントを入手しやすくなるでしょう。
- 自分の専門性とは異なる領域の知見
看護部長になるような方は自己研鑽を積み重ねている人材が多いと思いますが、だからと言ってすべての診療科に精通するようなことは、現実的に難しいはずです。一人の人間が、あらゆる領域で豊富な知識や経験を持ち合わせることはできないからこそ、他者の知見を取り入れることが重要です。私自身も、看護部長だからと言って完璧をめざす必要はなく、強みを持ち寄って関係者全員で前進していけばいいと考えています。より多角的な視点から適切な解を導き出すためにも、外部顧問の活用は有効です。
- 任期に振り回されない継続的なサポート
DX推進のためには、長期的な見通しで計画を作成し、適切な予算を確保する必要があります。新しいシステムや技術を導入する際には、職員が慣れるまで時間がかかるため、即座に業務改善を図れるとは限りません。すぐには成果が実感できないばかりか、費用対効果が一時的にマイナスになる可能性もあるので、5~10年先を見据えた導入成果を想定して決断する必要があるのです。
このような状況下で必要となるのが、導入経験が豊富な顧問からのアドバイスです。自身の任期のことを考えると、長期的な計画を立てづらいことがあるかもしれませんが、第三者による継続的なサポートがあるなら話は変わってきます。さらに、予算を確保する際には、感情面や情緒面に訴えるだけでなく、コストや費用対効果を明確に示すことが求められます。この点においても、外部顧問は冷静で論理的な交渉をサポートできます。
急速に変化する医療業界を生き抜くために、医療分野に特化したサービスの必要性が高まる一方で、まだまだ集約的なサービスは少ない現状があります。マイナビ医療・介護経営は、当分野に特化した新たなビジネスモデルとして展開されており、先駆けのサービスだと感じています。将来を見据え、特に経営が厳しい急性期病院や廃業が続く個人病院などにおいて、本サービスを活用して競争力を高めることを検討いただければと思います。
DX推進について共に考え、歩んでいきます
どれだけ優れたシステムを導入しても、単独で使用するだけでは医療DX本来の力を発揮することはできません。例えば、電子カルテはそれ自体で便利なシステムですが、シリンジポンプや人工呼吸器といった他の医療機器と連携することで、さらに幅広いサービス提供が可能になります。
現在の日本では、各組織が「縦割り」で動きがちで、組織内外での情報共有や連携が不十分になりがちだと感じています。オープンイノベーションが盛んに行われ、各医療機関や企業の強みを統合することで製品開発を進めているアメリカのような仕組みを積極的に取り入れ、日本の医療DXがより加速することを期待しています。また、私自身も医療現場と開発現場をつなげる一助になりたいと考えています。
将来的に、院内のさまざまな機器が連動・連携できる環境が整っていけば、業務効率の大幅な向上や看護ケアの質のさらなる向上が期待できます。どのような課題から手を付けるべきか分からない場合でも、ぜひお気軽にご相談ください。私と一緒に、貴院に合ったDXの在り方を見つけていきましょう。
医療DX推進

関西エリアの急性期病院で活躍する看護部長
S専門家
その他「医療DX推進」を得意とする専門家は複数います。お気軽にご相談ください。
関連する資料・ホワイトペーパー
White Paper