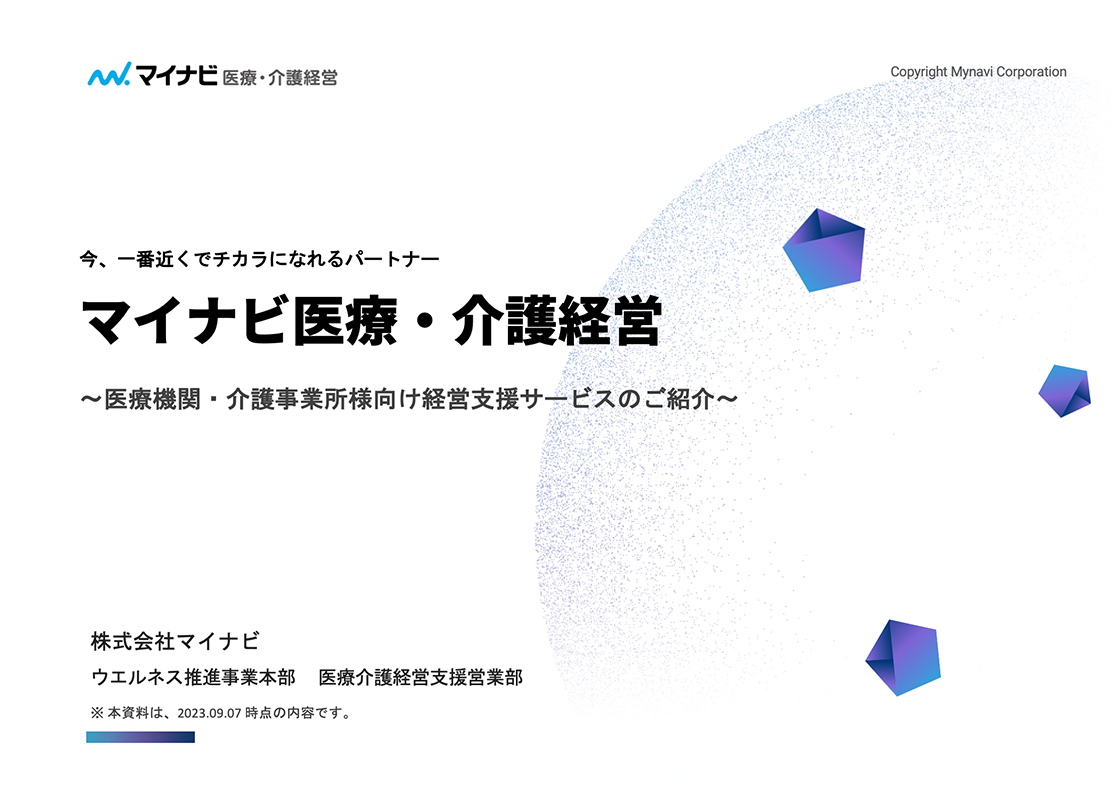このような課題を解決したい方へ
- 安定的・成長性のある経営で地域に貢献したい
- 介護保険制度の改定により営業利益が下がってしまった
- 経営課題に関して正確に現状を把握し、改善へ向けて取り組みたい

多岐にわたる領域で経営改善の実績を持つプロフェッショナル
マイナビ医療・介護経営の登録専門家:菅原隼人氏
時代の流れとともに、介護業界を取り巻く環境はますます厳しさを増しています。「人手不足が一向に解消されない」「効率化を図れず利益が圧迫されている」「将来的にはM&Aも検討したいが専門知識がない」など、悩みを抱えている経営者も多いのではないでしょうか。
マイナビ医療・介護経営で活躍中の菅原専門家は、経営管理や人材マネジメントなどを通して数々の実績を上げてきた人物です。これまで関わってきた領域は、在宅事業(訪問介護、居宅介護支援)、特別養護老人ホーム、介護タクシー、訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護、グループホームなど多岐にわたります。「売上予測の精度向上により売上高を前年度比10%増加」「コスト削減により利益率を前年対比20%改善」「KPI管理の強化により生産性30%向上」など、その成果は数値でも実証済み。東日本大震災後、わずか2カ月で売上をV字回復させたこともあります。
介護業界の法人が安定的かつ成長性のある経営を実現し、長きにわたって地域に貢献し続けるためには、どうすればいいのでしょうか。菅原専門家に、マネジメント層が知っておきたいポイントについてお話を伺いました。

中小法人に厳しい環境、生き延びるためには
2000年に介護保険制度がスタートし、早25年がたちました。私はこれまで15年以上、介護領域を中心にマネジメントを担ってきましたが、特に近年では業界を取り巻く状況の厳しさを肌で感じています。介護報酬改定の内容は毎回、各領域の法人にとって厳しいものであることが多く、その最たるものが2024年度改定における「訪問介護サービスの基本報酬引き下げ」でしょう。一方で、職員には処遇改善を図る必要があり、営業利益が下がらざるを得ない状況が続いています。もともと利幅の小さい中小法人では耐え切れず、倒産・休廃業に至るケースが増加していることは皆さんもご存じでしょう。
こうした状況下で、世代交代のタイミングなどでM&Aを検討する法人も増えています(実は私のところにも、多いと月10件以上も相談が来ています)。しかし、すでに経営状態が厳しくなっている法人、特に債務超過しているようなケースでは、譲渡先を見つけることが容易ではありません。少なくとも、当事者が期待するような額ではM&Aが成立しないことが大半です。本来、M&Aは「業績が一番伸びているとき」に検討することが理想的で、タイミングを見誤れば交渉は難航してしまいます。自力で経営を続ける場合はもちろん、M&Aという選択をする場合でも、まず経営改善に着手することは必須なのです。
介護業界の経営改善で必要な「3つの軸」

それでは、介護業界で経営改善を果たすために、具体的にどのような視点を持てばよいのでしょうか。私がこれまでのキャリアで感じてきた点を整理し、「3つの軸」としてお伝えします。
- 「数字」と向き合う
経営課題は、基本的に数字からしか見えません。人間が感じている課題感はあいまいだったり、不正確だったりすることも多いもの。例えば、同じ状況下でも、物事を自責で捉える人と他責で捉える人では大きく見方が変わってしまいます。最も正直で嘘をつかない数字ベースで、より正確に現状を把握することが第一です。収益・費用の分析、予算や実績の管理、競合分析など経営にまつわる数字は多岐にわたりますが、ぜひ注目したいのがKPIです。
KPIとは、目標達成の進捗を評価するための指標のこと。決して難しく考える必要はなく、売上目標などを現場に分かりやすく落とし込んだものとイメージしてみてください。例えば、訪問介護ですと「最低60時間は正社員が現場に出る必要がある」、居宅介護支援事業所ですと「1人のケアマネジャーが持つプランの数は35以上」といったことです。各人の職責や役割に基づき、どのようなミッションを実行すればいいかを明確に示すことが大切です。こうして設定したKPIの達成率を追い、効果検証を続けていくことが経営改善の基本となります。
- 行動指針を明確化する
上記のKPIを設定するためにも、前提として必要になるのが行動指針です。行動指針がない状態でやみくもにPDCAを回しても、適切なバリューが発生しているかが判断できません。近年、他業界では「理念浸透型」の事業モデルが非常に重要視されています。経営者は法人の理念に対する思いを熱く語れることが大切であり、これは介護業界においても共通です。しかし現実には、この行動指針を置き去りにしている法人が非常に多いのです。実情としては、思いはあるのにうまく整理・言語化できておらず、理念を掲げていても抽象的になりがちという傾向があります。法人の理念実現に近づくことで世の中にバリューを生み出し、その対価として収益が得られるという仕組みの全体像を、あらためて振り返ってみましょう。
なお、理念そのものが古くなっていないかを確認することも重要です。例えば、利用者を対等な目線で捉えず、「助けてあげなければならない人」とみなすような文言には、世の中の流れから取り残されているような印象を受けます。今の時代に合った言葉選びを心がけましょう。
- 「当たり前」を徹底する
介護事業はボランティアではなくサービス業であり、利用者から選んでもらうことが欠かせません。しかし、介護保険制度という縛りがある以上、特別な取り組みで企業価値を上げることは難しいでしょう。そこで大切なのが、「当たり前」を徹底することです。皆さんの事業所の職員は、朝、利用者さんに会ったら「おはようございます」と目を見てあいさつしていますか。こうした相手へのリスペクトがある言動を貫くことが企業活動の大前提であり、すべてであるとさえ言えます。このマインドが現場に徹底していれば、虐待の問題も起こりにくいと考えられます。
私が在宅事業に関わって思う事は、在宅療養の要である訪問診療の医師に、必ずやってもらっていたことが2つあります。1つは、帰る前に利用者さんの手を握り、しっかりと目を見て「お大事に。〇週間後にまた来ますね」と伝えること。もう1つは、利用者さんとの会話を記録に残し、次の訪問時に「前回の会話の続き」ができるようにすることです。特に後者は優秀なサービス業の方、例えば美容師さんなどもよく実践していること。安心感や信頼感を育み、しかもコストは1円もかからない優れた手法です。
在宅事業で売上V字回復を果たした背景には……
これまで、さまざまな組織で経営改善に取り組んできましたが、中でも印象深い事例をご紹介しましょう。27歳の年、当時勤めていた会社で福島県への転勤を命じられ、現地の訪問介護の2つの事業所を立て直した時のことです。当初、その事業所は月の売上100万円程度の規模感で、転勤から半年ほどは1件も新規契約ができない状態でした。しかし、そこから約2年間で顧客数は10倍ほどに増加し、年間の売上高も1億円超まで伸ばすことができたのです。この急成長の背景で、私が意識していたことは次の3点でした。
- しつこいと言われるほどの営業強化
「また来たの」と言ってもらえて、初めて認知されている状態と言えます。相手の印象に残るためには、直接の訪問に加えて、毎週決まった曜日にチラシをFAXすることがポイント。習慣的に同じものを目にすると、知らず知らずのうちに頭にインプットされていくからです。相手と話す時にも、事業所の情報を一方通行で伝えるのではなく、相手との会話のやり取りの中でニーズを引き出す話術が求められます。専門職がその力を発揮するためには、サービスの受け手を獲得することが大前提。待ちの姿勢ではなく、積極的にアピールすることが肝心です。
- 担当者によらず高品質なサービスを
訪問介護サービスを提供する上では、年齢も経験も異なるさまざまなホームヘルパーと関わります。大切なのは、誰がサービスに入っても変わらないクオリティーを提供すること。しかし、各人が訪問先でサービスを提供するため、質の担保は想像以上に難しい課題です。そこで私は、ホームヘルパーが入っている時間帯に、突然自分もおじゃまする「抜き打ち訪問」を実施。あら探しではないので、現場で起きたことを責めたりはせず、何も言わず見守ることを意識しました。この訪問が、ホームヘルパーが常に緊張感を持って仕事に臨むこと、ひいては質の向上につながっていったのです。
- 上司としての振る舞いを試行錯誤
職種によっても、上司に求めるものは違います。例えば、看護師は自分の仕事に誇りやプライドを持っています。レベルの高い上司であることを求める傾向にあると感じました。こうした要求に応えられるよう、立ち居振る舞いや言葉遣いを改め、話し合いを進める上では客観性のあるデータを出すことを意識。さらに、草むしりなどの雑用を自らこなす姿勢も大事にしました。職員が「この人についていきたい」と思うような人間であることが、マネジメント層には求められます。自分が相手からどのように見えているかを意識し、うまくセルフプロデュースする視点を持ってみましょう。
「エラーが起きた時」を支え、現場に成功体験を

私が組織の立て直しを図る際に心がけていることは、そこで働く人々のことを知る努力を惜しまず、本気で向き合うことです。少し古い考えかもしれませんが、「同じ釜の飯を食う」といった感覚はやはり大切で、他人事と思わずに取り組む姿勢が欠かせません。いくら経営手腕に優れていても、リスペクトできない人間の話は聞いてもらえませんから、尊敬や感謝の姿勢を自分から示すことを第一に考えています。
また、現場でお困りの皆さんに「成功体験」を得てもらい、自信を持ってもらうことも重視しています。特にポイントとなるのが、トライアンドエラーを重ねる中で「エラーが起きた時」の対応。冷静に事態を分析したり、次から回避する方法を一緒に考えたりして、改革が停滞しないよう背中を押すことが私たち専門家の役目だと考えています。こうしたサポートを得られることが、外部の人間の手を借りる最大のメリットであり、マイナビ医療・介護経営に依頼する意義でもあります。目前に迫る経営課題を乗り越え、組織が前に進む力を得るために、ぜひ遠慮なく私たちを頼っていただければうれしいです。
介護事業における経営戦略・マネジメント 専門家

菅原 隼人専門家
その他「介護事業における経営戦略・マネジメント」を得意とする専門家は複数います。お気軽にご相談ください。
関連する資料・ホワイトペーパー
White Paper