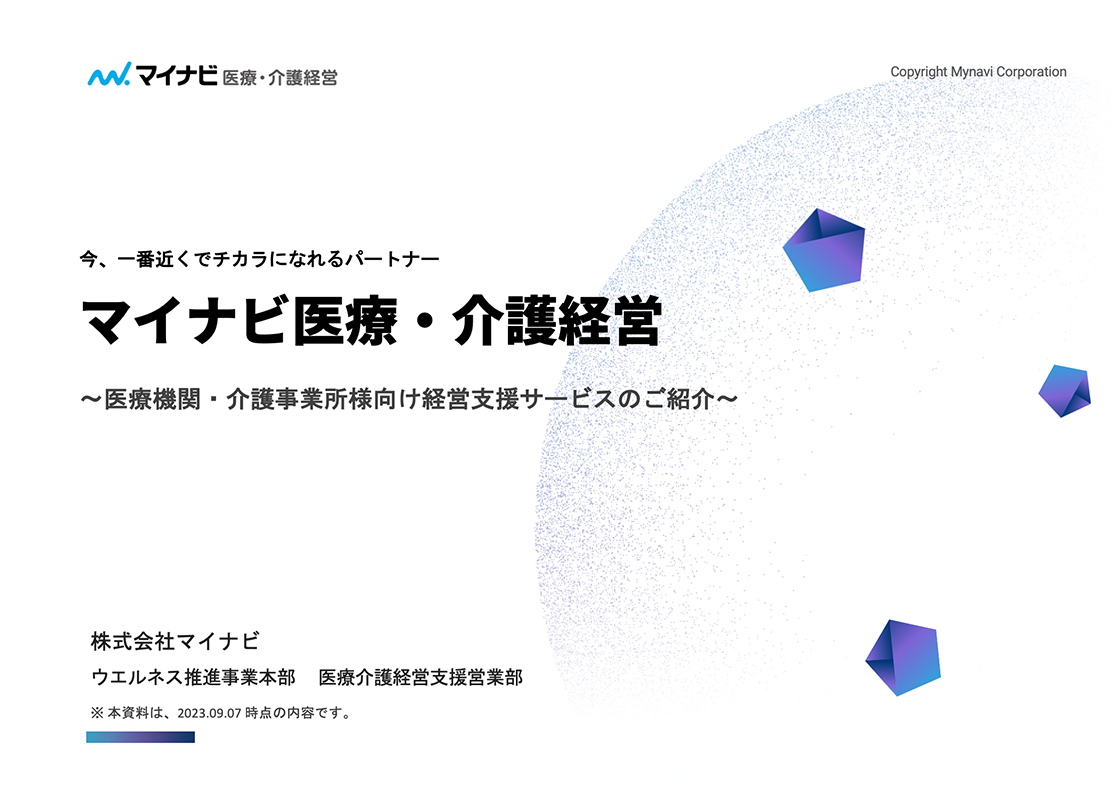このような課題を解決したい方へ
- どのような方向性で経営方針を設定したらよいかわからない
- 人事制度の見直しを行い、自発的に職員が動くような組織を目指したい
- 世代交代における病院経営を円滑に進めたい

経営課題を見極め組織改善で解決を図るーー医療機関・介護施設向け経営支援
マイナビ医療・介護経営の専門家: 株式会社ReVOYL 代表取締役 飯田 哲哉 氏
進まない世代交代、赤字が続く経営状況、迫られる働き方改革。医療機関・介護施設の経営は時代の変化と共に厳しさを増しています。自力で経営改善を図ろうにも、現状を紐解き問題の根幹に気づくことは容易ではありません。そのような時には第三者によるアドバイスで解決の糸口が見つかるかもしれません。令和の時代における医療機関・介護施設の経営支援はどのようなものなのでしょうか。20年以上にわたり、医療機関・介護施設の経営をサポートしているマイナビ医療・介護経営。その専門家でもある飯田哲哉氏にお話を伺いました。

求められる医療機関・介護施設向けの経営支援
昭和・平成・令和と時代が大きく動き、医療機関・介護施設経営も、年々厳しくなっています。院長や事務長など経営陣の高齢化による世代交代やM&A、集約化が進み、一方で経営の詳細が明確でない法人も多くあり、経営支援へのニーズは高まっています。
医療機関・介護施設が淘汰される時代の中、経営者が直面している問題は利益が出ていないことや、キャッシュフローがマイナスになっていることが多いようです。なぜ利益が出ていないのか、その詳細を各医療機関・介護施設が把握できている・できていないは分かれるところです。
例えば「売上が上がらない」という悩みを抱える病院の事務長は多くいますが、診療報酬に左右される中で、単純に売上だけが問題なのか、売上低下の背景について分析する必要があります。特に今回は診療報酬と介護報酬の同時改定が行われている中、どのような方向性で経営方針を設定するか多くの病院が悩みを抱えています。
また、大きな経費である人件費に目がいきがちですが、他の経費の上昇について評価できていない、そもそもそこに目を向けられていないこともあるので、一度俯瞰して定量的に経費を分析する機会を持つことも必要です。それらを見える化するだけでも「これは着手できそうだ」「これは根深い問題だ」「これはこういう問題があって解決が難しい」と具体化につながるため、優先順位をつけることができ、経営の見通しをたてることができます。
実はこうした問題に事務長や経理課長は気づいていることもありますが、経営者とコミュニケーションが取れていないため実行に移せないことも少なくないようです。専門家という立場だからこそ経営者に提案することができ、解決のきっかけになることもあります。
外部支援を求めるタイミング

では、どのタイミングで外部支援を検討すればいいのでしょうか。私は以下のタイミングで導入することをお勧めしています。
- 2~3年間赤字が続いている場合
長期間の収支赤字やマイナスのキャッシュフローは、自力での対処が難しいため、一度外部の支援を求めることをお勧めします。最近は金融機関が危機感を持ってコンサルタント等を紹介してくることもあります。 - 赤字ではないが成果が出ていない場合
黒字になったものの期待する数字ではなかったり、一時的な黒字にとどまったり、再び赤字になったりする場合もあります。このような場合、組織が円滑に機能しておらず、人間関係や部署間あるいは職種間の関係性、上司部下の関係性などの問題が背景にあることが多いです。自発的に職員が動くような組織を目指すためには、人事制度の見直しが効果を発揮する場合が多いです。コンサルタントに長く伴走してもらうよりも、職員が目標に向かって一緒に考え解決していける組織を育成する方が望ましく、そのためには、職員の成長を後押しするような人事制度を考えていけるサポートが必要だと思います。
経営改革に必要なのはダイナミックな組織変化をマネジメントできる人材
診療報酬や介護報酬の変化に対応できているか否か。それが経営がうまくいくかどうかの分かれ道となります。昨今の診療報酬の変化に対応するには、ある程度組織をダイナミックに変化させていくことが求められ、自部署だけでなく多職種も巻き込んでその変化に適応しマネジメントできる人材が求められています。
しかし、優秀な事務職員を育成できるプログラムを法人内で持てるかというと現実は難しく、銀行や公務員のOBに事務長・経理部長の役割を見出そうとする場合もあります。しかし、医師や看護師とのコミュニケーションが難しかったり、一般企業とは異なる経営の舵取りに困難を抱えたり、なかなか順風満帆とはいかないようです。
経営陣の世代交代が大きな課題

昨今の病院経営における大きな課題は世代交代です。昭和の終わりから平成にかけて開院し、経営者である理事長や院長、事務長が70~80代になり、体力的に厳しくなってきたり、複雑化する診療報酬への対応が難しくなったりして世代交代が迫られています。子どもに経営を託したいと思っても、まだ経営者になるには臨床経験も経営スキルも足りず、世代交代できないまま病院経営が低迷してしまうのです。
また、考え方の変化として、採算度外視で「とにかく患者を診よう」という価値観や、地産地消と手作りにこだわった病院給食を提供することで経営を圧迫している先代と、IT化を進めたり、DX導入や業務委託の活用によって効率化をはかりたい子世代とのせめぎ合いなどを目にすることがありますが、そのような価値観の不一致も、世代交代を阻む要因です。
さらに、職員の中にもかつての事務長や看護部長を慕っていたメンバーもいれば、新しく入ってきたメンバーもいるため、世代交代は組織的に大きな痛みを伴うことが多いです。私が仲介して両者の誤解を解いたり歩み寄る役割を担い、いかに少ない痛みで世代交代するかを考えています。また、世代交代したとしても、その医療機関・介護施設の理念や文化、物語を引き継いでいくことを重視し、できるだけスムーズに進められるような支援をしています。
介護施設の経営支援は現場スタッフと共に
介護施設の経営支援で問題になっていることは業務効率化です。フロアスタッフの何人もが同じことをしていたり、人員が少ないため、朝5時から入居者の歯磨きを夜勤者が行っている施設を見たことがありますが、これは問題だと思います。すべて「人材不足」と一括りにされがちですが、もっと効率的に業務を進めるためにはどうすればいいのかを第三者的に関わることがあります。どこの介護施設であっても、一週間のタイムスケジュールを作り、現場で誰が何時から何時まで何をするのかを可視化すると改善ポイントが分かりやすいです。
それにより、この時間帯にこのケアをするのは無理があるのではないか、また、昼休みが30分しか取れないのはここに問題がある、ということが見えてくるようになります。そのため、一緒に問題解決をはかっていきます。一定のルールを設けることで、それぞれが自発的に動く組織に成長します。
介護職の方たちは「介護が好き」でこの仕事に就いていることが多く、勉強熱心で業務改善に協力的です。役職についていなくても、「利用者さんに関わる時間をいかに確保するか」というテーマでは、皆さん同じ目標に向かって考えてくれるようになります。例えば「このデイサービスの送迎時間を20%短くする方法を一緒に考えましょう」と投げかけるとたくさんのアイデアが出てきます。
救急患者の受け入れツールを作成して収益改善

収益を大きく改善できたケースがあります。当直医の診療科が毎日違うため、夜間に救急車を受け入れても、その後当該診療科との連携がうまくいかない事象がたびたび発生し、救急患者を受け入れたくても受け入れられない問題を抱えている病院がありました。例えば肺炎で内科的治療が必要な患者の受け入れを、消化器外科の当直医が躊躇するというパターンです。
そこで、救急外来および院内の各診療科・各部門で何が問題なのかを定量的・定性的に分析しました。そして、すべての診療科・部門で「この状態・この疾患であれば受け入れ可能」という基準を明文化し、すべての当直医が一定の基準で救急患者の受け入れを判断できるようにしました。その結果、救急患者の受け入れ件数が増え、収益改善につながりました。
また、中小規模病院では不採算の診療科を整理することもあります。例えば月2回形成外科外来を開設し、非常勤の医師に1日10万円の給料を払うものの売上が1日3万円というケースです。形成外科は入院診療においても役割がありますので単純には整理できませんが、損失の大きな場合には検討が必要です。さらに、非常勤の問題は看護部でも顕在化しており、看護師の常勤化を進めたり、派遣委託に頼っているところを常勤化することで、問題の解決をはかっています。
レッドオーシャンな医療・介護コンサルタントを見極め、経営改善を
需要の広がりを受けて、医療コンサル会社や医療コンサルタントが増えており、どこに・誰に依頼すればいいのか、その判断基準は難しいかもしれません。また、過去に依頼したものの成果が出なかったという苦い経験をお持ちの法人もあり、次回の依頼をためらうこともあるでしょう。
まず、コンサルタントに依頼する前に法人としてすべきことは、ニーズをはっきりさせることです。もし、ニーズがはっきりしないのであれば、ニーズをはっきりさせてくれる人に依頼すべきです。実行はまた別の人でもいいでしょう。分析から実行シーンまですべてを求めると大きなプロジェクトになりますし、途中で折り合いがつかなくなる可能性もあります。
マイナビ医療・介護経営では、ダイレクトにプロフェッショナル人材を探せるため、ニーズさえはっきりしていれば、とても活用しやすいサービスだと感じています。プロフェッショナル人材を短期で雇用できるというコンセプトなので、大きなコストをかけずに短期集中的に、そしてリーズナブルに医療機関・介護施設の問題を解決できることは大きなメリットです。
経営改善のために、自分たちで何とかしようとせず、豊富な現場経験を持つプロフェッショナル人材を使い倒すくらいの気持ちで活用していただければと思います。スピーディーに進めていかなければ患者さんも離れてしまいますし、同じ地域のライバル病院から遅れをとってしまうことにもなります。現場経験があり円滑なコミュニケーションがとれるコンサルタントは、経営者ともスタッフとも、パワーの強い方ともコミュニケーションをとることができ、組織を元気にし、本質的に問題を解決へと導いてくれるはずです。
医療機関の経営課題 専門家

株式会社ReVOYL
代表取締役
飯田 哲哉専門家
その他「医療機関の経営課題」を得意とする専門家は複数います。お気軽にご相談ください。
関連する資料・ホワイトペーパー
White Paper