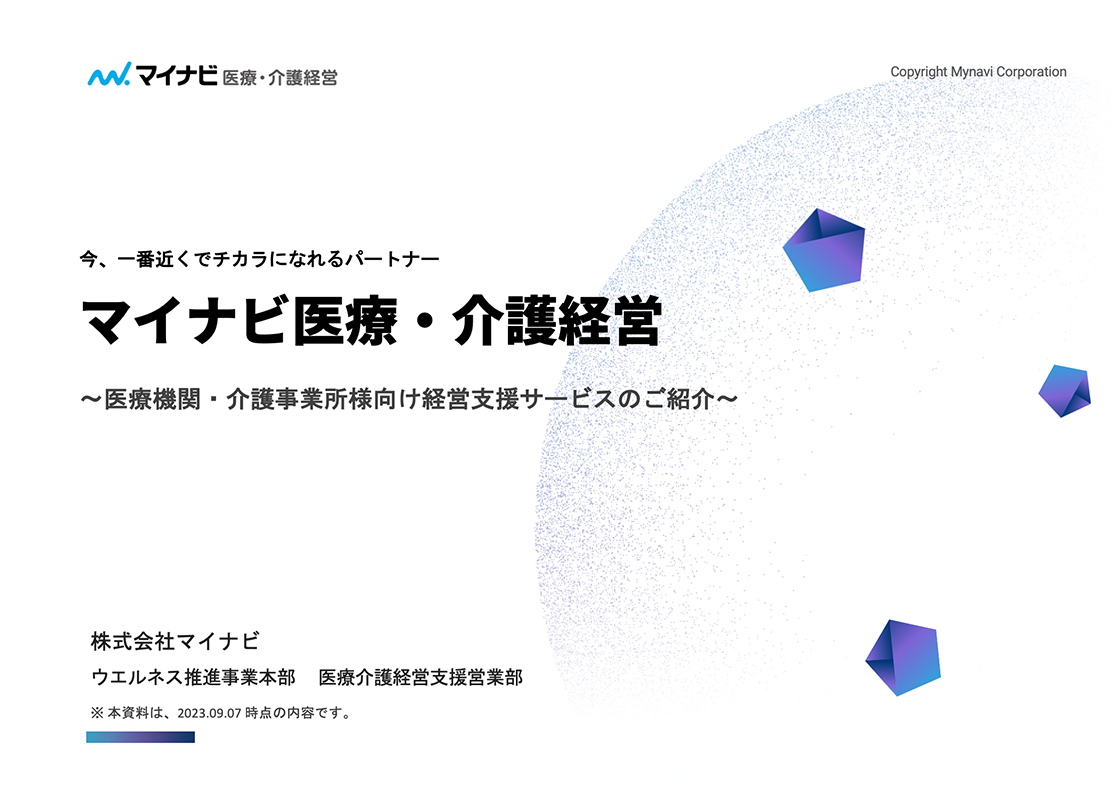このような課題を解決したい方へ
- 看護師の育成について課題を感じているが時間が割けず、後回しになっている
- 新人看護師の育成方法に課題を感じている
- 一人ひとりが自由にキャリアを考え、行動できる環境を作りたい

避けて通ることはできない、看護師の育成ーー教育研修
マイナビ医療・介護経営の専門家: 関西エリアの急性期病院で活躍している看護部長 S 氏
どの分野においても後進を育成することは重要で、看護も例外ではありません。しかし、看護師に対して「もっと積極的に動いてほしい」「さらなる向上心を持って業務に当たってもらいたい」と思っていても、忙しい医療現場では後進の育成に時間を割いたり、教育プログラムを見直したりする余裕がないことが多いのではないでしょうか。
マイナビ医療・介護経営の専門家として活躍中のS顧問は、急性期病院で手腕を発揮する、現役の看護部長でもあります。副部長に就任する以前から院内の改革へ次々と着手しており、こうした積極的な姿勢は看護部長になった今でも変わりません。S顧問がとりわけ重視するのが、看護に携わるスタッフ一人ひとりの能力を伸ばすことです。組織全体として、個々のやりたいことを尊重し、個性を伸ばす文化を醸成することに力を注いできました。現在では、新人採用を含めて幅広く人材育成に取り組んでいます。
少子高齢化により、今後ますます医療現場での人材不足が懸念されるからこそ、看護師の育成は避けて通れない課題でしょう。教育研修における考え方や重要なポイントについて、S顧問にお話を伺いました。

「新人教育」の現実と課題
まずは、早期の離職を防ぐためにも重要な、新人教育についてお話ししましょう。各医療機関で必要とされる看護師数をカウントする際には、1年目の新人看護師もベテラン看護師も同じように扱われます。経営側が「要員は足りている」と判断していても、実際の現場では、先輩看護師が新人の業務をフォローしながら必死に運営しているケースが少なくありません。限られた時間と予算の中で、新人看護師を1人でも早く成長させるためには、当事者のやる気や能力だけに頼るのではなく、院内全体が一丸となって支援する体制が欠かせません。
初めて医療現場に足を踏み入れる新人たちは、右も左も分からず、思うように動けないのが当たり前です。しかし、新人だからと特別扱いの手厚い教育支援制度やスローペースの指導は、私の勤める病院では行っていません。むしろ、現場教育(OJT)を充実させ、夜勤にも早い段階から入ってもらおうというのが私の持論です。人材を育てることの重要性は、決して新人時代に限った話ではありません。看護師として常に成長を追い求めるためにも、より長期的な目線で支援していく必要があります。
また、当院のOJTでは一対一でプリセプターを付けるのではなく、教育担当者が職場内にたくさん存在する「屋根瓦方式※」を採用しています。このアプローチにより、看護師同士の相性による問題が個人間で起こりにくくなり、チーム全体でサポートし合える環境を整えています。もちろん、成長レベルには個人差があるので、スキルがどんどん伸びていく人もいれば、予定通りに学びが進まない人もいます。そうした点はしっかりと考慮し、個々のペースに合わせた支援を実現しています。
※教えられた側が徐々に教える側に回り、屋根瓦のように重なって支え合うようなチーム指導体制のこと。
「キャリアサポート」の現実と課題

「入職してきた看護師は何が何でも自院で育て上げる」という考えを持つ医療機関が大多数かもしれません。しかし当院では、もし院内で実現できないことがあるなら、その看護師を現状に留めるのではなく、他の環境で成長を続けられるように支援する方針をとっています。もちろん、当院を卒業する看護師が次のステップで活躍できるためにも、キャリアサポートを念頭に置いた教育システムの充実は非常に重要です。こうした意識を持って教育システムを改善し続けてきた結果、それに魅かれて入職・転職してくる人材も増えました。例えば、2~3年目の看護師であれば、院外で論文などを発表できるレベルまで文章力を鍛え上げます。また、キャリアアップについて学ぶ機会も設け、認定看護師などスペシャリストをめざすための支援も積極的に行っています。
スペシャリストをめざすという観点では、私自身の経験や知見を教育に活かすことができる場面も多いです。看護部長である私がさまざまなことに取り組む姿を見て、師長をはじめとする管理職の中でも、キャリアアップを意識する人が増えているようにも感じます。現在、当院で認定看護師として活躍する看護師は全体の6.4%を占めますし、特定行為研修を受ける看護師も少なくありません。新しいことに挑戦するのは非常に勇気がいることですが、こうしてロールモデルとなる先輩が何人もいれば、実体験を聞くなどして不安な気持ちを解消し、前進しやすくなるのではないでしょうか。
私が大学院に通学していた時期を思い返しても、不安な気持ちは少なからず抱えていました。当時、マネジメント職として働きながら大学院に通うという前例が周囲になかったので、とてもハードルが高く感じたのです。もしも当時、組織に大学院卒業生がいれば、費用面や負担感、スケジュール感といった気がかりを、ある程度事前に解消してから行動できたと思います。先輩の背中を見て「私もやってみたい」「あんな看護師になりたい」と憧れる後輩が増えることは、組織にとっても非常にプラスになります。前例がなければ、そもそも「スペシャリストをめざせる道がある」と認識すらできない可能性もあるため、キャリアサポートにおいては多様な選択肢を示すことが重要なのです。
看護師育成で重要な3つの視点
それでは、私がこれまでのキャリアで感じてきた、看護師育成における3つの重要な視点をお伝えします。
- 自由に行動しやすい雰囲気をつくる
一人ひとりが自由にキャリアを考え、行動しやすい環境をつくることが大切です。集団の中には「自由に行動する人を快く思わない人」も存在するものですが、そうした負のオーラに影響を受けることのないよう、各自が力を発揮できる現場を管理職が整えることが求められます。ポジティブな影響は「連鎖」していくもので、生き生きと行動している姿に触発される人が増えていけば、やがて組織全体の良質な文化や土壌を形成することにつながります。
- 「外の世界」について積極的に伝える
他院の取り組みや看護師の活躍を知って刺激を受けると、自分たちの強みや弱みが浮き彫りになってきます。また、内向きだった視野が広がることで、新しいことに興味や関心が湧いてくる効果も考えられ、管理職が積極的に情報提供することが望ましいでしょう。他院の情報を知る機会はそう多くないと思われがちですが、さまざまな病院に卒業生を送り出している看護学校は、そうした情報を豊富に持っている可能性があります。病院と看護学校が積極的に情報交換する仕組みがあれば、看護師業界はもっと活性化していくはずです。
- 個人の能力を伸ばすことで全体を底上げする
一人ひとりが自分の強みを見つけて伸ばすことで、看護の質が底上げされ、他のメンバーのレベルアップにもつながります。それを実現するためには、院内共通の教育システムを充実させることに加えて、各メンバーが自分の道を見出せるよう上長が寄り添い、支援する姿勢が欠かせません。信頼できる先達と語り合い、自分の今後を一緒に考えてもらえる時間は、看護師として前進する上で心の支えになります。個人が自信を持って成長できるようサポートすることで、最終的には組織全体の力が高まり、多様性が高まることにもつながっていきます。
外部講師を上手に活躍するためのポイント

教育研修のために外部講師を依頼しようとしたとき、知り合いや周囲の評判に頼る方法が一般的ですが、どうしても検索範囲が狭くなりがちです。依頼したいテーマに精通した講師を見つけるためには、限られたネットワークの枠を広げたアプローチが重要です。そのためには、外部のコネクションや専門的な仲介サービスを活用することも有効な手段になり得ます。信頼できる仲介先を利用すれば、講師の多様性や質が担保され、管理者としても安心して依頼することができます。多様な講師との出会いは、看護師たちが新しい視点や価値を見出す貴重な機会になるでしょう。
適切な講師を選ぶことは、研修効果を最大化するための重要なステップです。従来、講師選びは限られたネットワーク内に留まりがちでしたが、マイナビ医療・介護経営に登録されている専門家に目を向けていただくことで、より多くの適切な人材に出会える可能性が広がります。
教育支援を通して、現場にエールを届けたい
これまで私は、自身の専門分野である「感染対策」を最大の武器にして、感染管理認定看護師の認定を取得したり、学会発表に取り組んだりしてきました。現在では、看護部長として培った知見を活かし、日本各地で非常勤講師なども務めています。
自分の役割は、未来の医療を支える看護師たちが生き生きと働き、自身のキャリアに希望を持てるよう、教育研修を通じてエールを送り続けること。こうした思いから、オンライン研修よりも対面研修であることを重視し、聞き手の興味や関心に合わせて柔軟な内容を提供しています。また、研修後の交流から新たなつながりが生まれることも多く、人と人との温かい関係が築かれることも、リアルで教育の場を設ける大きな魅力だと考えています。
心の通った教育を提供すること、そして温かいつながりの輪を広げていくことを通して、私のメッセージが未来の医療を支える看護師たちの力になれば幸いです。この記事をご覧いただいた皆さんと、教育研修の場でお会いできることを楽しみにしています。
教育研修

関西エリアの急性期病院で活躍する看護部長
S専門家
その他「教育研修」を得意とする専門家は複数います。お気軽にご相談ください。
関連する資料・ホワイトペーパー
White Paper