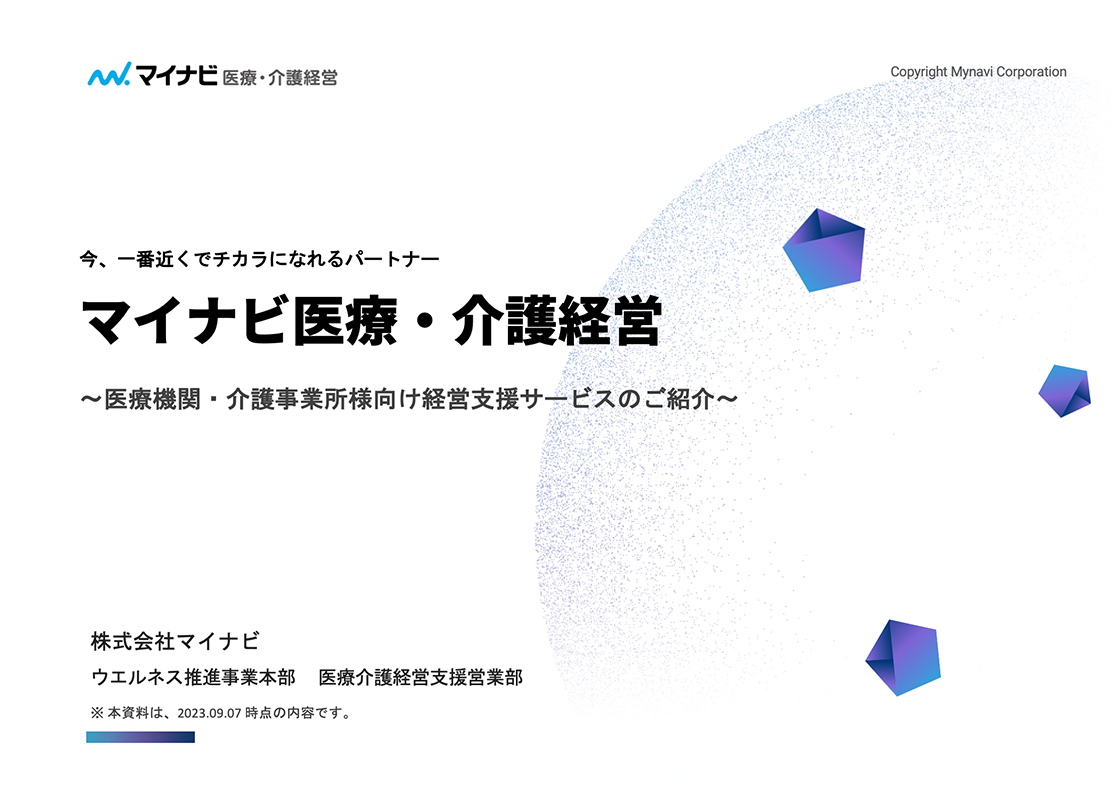このような課題を解決したい方へ
- 社内のハラスメント対策を実施したい/内容についてアドバイスが欲しい
- 時代に適した指導方法をアップデートし、職場環境を改善したい
- 急増しているカスタマーハラスメントから従業員を守りたい

社労士と共に目指す風通しのいい職場環境ーー医療機関・介護現場のハラスメント対策
マイナビ医療・介護経営の専門家: 社会保険労務士法人ベスト・パートナーズ 代表社員 米田 憲司 氏
近年、パワハラ、セクハラ、モラハラなどのさまざまなハラスメント対策に頭を抱える経営者は多いのではないでしょうか。法整備によって改善が進められているものの、現場では今なお多くの課題を抱えている…といったお悩みを耳にします。ハラスメントのない快適な職場を作るためには、そしてハラスメントに関連するさまざまな問題を解決するためには、経営者としてどのように行動すればいいのでしょうか。また、2025年4月に全国初となる東京都でカスタマーハラスメント(カスハラ)防止条例が施行され、他の都道府県や国も法制化に向けて議論を進めており、喫緊の課題ともいえます。
職員が傷つかないようにするために、経営者が取り組むべきことについて、医療・介護現場の労働問題に精通する社会保険労務士で、社会保険労務士法人ベスト・パートナーズ代表社員の米田憲司専門家にお話を伺いました。

変化する医療・介護業界のハラスメント
医療・介護業界は人によって成り立つ「労働集約型」の産業です。人が動かなければ業務が遂行できず、人と人との密着度が高かったりすることから、ハラスメントが発生しやすい環境が生まれやすく、問題も多く存在しています。
2019年に「労働施策総合推進法」(いわゆる「パワハラ防止法」)が改正され、職場でのパワーハラスメントに対して事業主に防止措置を講じることが義務付けられました。これを契機に、社会に広く認知され、今まで自分が受けていた行為がパワハラだったと気づく人も多くなり、問題が表面化するようになりました。特に医療・介護業界はその特性からパワハラが多くみられ、定着率などにも大きく影響しています。また、サービスや医療技術の質にも影響を与えていると推察されます。
一方で、最近は上司から何か言われた際に「パワハラだ」と言えば、すべてが免責されるような手段として使われることもあります。このため、上司が部下に指導しづらい環境が生まれ、指導やアドバイスの方法に頭を悩ませる管理職が増えています。技術の向上という視点からみると、これには難しさが伴います。かつてパワハラを受けて育ってきた人たちが管理職になると、「私も昔こう指導されたから」と、過去の指導法を繰り返すことがありますが、これは誰にとっても幸せな結果をもたらしません。今後は、私たちが実施する管理職向けの教育研修を通じて、時代に適した指導方法にアップデートしていく必要があります。
【参照】厚生労働省『職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!』|厚生労働省
相談件数ナンバーワン「看護師のハラスメント」

病院から寄せられる相談案件の中でも最も多いのは、看護師間のトラブルに関することです。これらのトラブルの多くは病棟など所属部署内で組織的に行われ、いじめや嫌がらせ、あからさまな無視や陰口がほとんどです。こうした問題が蓄積することで職場環境全体が悪化し、ハラスメントを受けた本人が離職するだけでなく、離職の連鎖につながっていく可能性が高まります。
最近はトラブル解決に向けて、ハラスメントの通報窓口を設置し始めた医療機関・介護施設が多く、そこから問題が発覚することも増え、ハラスメントをする人にとっては生きづらい世の中に変わりつつあります。しかし、それにも関わらず、我々のところには日々、事務長等から自院で解決できない問題に関する相談が寄せられています。
巧妙化するハラスメントに立ち向かうのは経営トップの強い決意
その理由として、ハラスメント形態が変化していることが挙げられます。一昔前は、暴力やその他の身体的攻撃が多くみられましたが、これらがニュースなどで報じられ、「暴力はよくない」との共通認識が形成されました。それと相まって、最近では身体的攻撃は非常に少なくなり、代わりに精神的攻撃が主流になっています。具体的には、先ほどの看護師のハラスメントに見られる無視や仲間外れ、人間関係からの切り離しといった情緒的な嫌がらせや、チームからの孤立を図るハラスメントが散見されます。身体的攻撃の場合、あざや骨折、あるいは叩くシーンを誰かが目撃するなどの証拠が残りやすいのに対し、精神的攻撃は目に見える証拠が残りにくく、組織的に行われるため発見に時間がかかります。例えば、ある病棟で看護師の離職が続くことに疑問を感じた経営陣が調査したところ、初めてハラスメントの実態が明らかとなり、どのように対応すればいいのかと相談が寄せられたこともありました。
このようなハラスメントが起こりやすい組織風土を変えるためには、問題が発生している部署の人員配置を検討することはもちろん、1つの病棟で生じている問題を病院組織全体の問題として捉え、対処することが求められます。また、問題を根本から解決するためには、理事長や院長などの経営トップ層によるハラスメント対策の方針表明が必要です。その上で研修などの施策を実施し、職員に対して徐々に意識を浸透させ、ハラスメントが起こらない環境を整えていきます。経営トップ層はハラスメントが経営上非常に重要な問題であると深く認識し、対策を実行に移していく力が求められます。
増加する偽りのメンタル不調への対応

近年、ハラスメントを起因とする適応障害による休職が増加しており、メンタルヘルスは重要な健康課題の1つとなっています。休職やカウンセリングを経て職場復帰する方がいる一方で、一部の誤解を招く対応に苦慮するケースがあります。上司からの注意に真摯に向き合わず、「ハラスメントを受けてしんどくなった」とメンタルクリニックを受診し、適応障害や抑うつ状態の診断を根拠に病院や勤務先に対して意図的に行動を起こす事例が増加しています。都市部は多数のメンタルクリニックが存在し、その中には患者本人が希望した通りの診断書を記載するクリニックもあるようで、インターネットで検索して受診し、その診断書を会社に提出して休職、そして傷病手当金の給付を受けて生活するというケースもあるようです。
以前、メンタル不調を理由に休職している看護師の方が、休職期間中にレジャー施設に行き、場内で撮った笑顔の写真をSNSに上げていたことがありました。職場の規定ではそのような行動は治療専念義務違反に該当するため、退職に向けた話を始めましたが、主治医が「この方のメンタル不調を改善するにはレジャー施設に行くことが効果的だ」と記載した診断書を提出してきたケースもありました。
主治医の意見はもちろん重要ですが、一般的に考えて、適応障害や抑うつ状態で会社を休んでいる間にレジャー施設に出かけるという理論は納得しがたいものです。別の医師によるセカンドオピニオンを求めましたが、就労に問題があるかどうか証明を拒否したため復職の判定ができず、最終的に休職期間が満了し、退職に至りました。
このようなケースで提出されるメンタル不調の診断書は、初診日に記載されたものが多く、そのため信頼性に疑問が生まれます。最近、司法の場では初診日に記載された診断書は信憑性が低いとされる傾向があり、「診断書さえ出せば何とでもなる」という状況は改善されつつあるように感じます。
間もなく義務化されるカスハラ対策で職員を守る
最近、カスタマーハラスメント(カスハラ)に悩む医療機関や介護施設が急増しています。これを受けて、2020年6月1日から大企業が、2022年4月1日から中小企業を対象に労働施策総合推進法が改正され、雇用主は従業員をハラスメントから守る対策をとることが義務化されました。東京都は全国で先駆けて2025年4月に「東京都カスタマー・ハラスメント(カスハラ)防止条例」を施行し、カスハラの減少が期待されています。
経営トップとして行うべきことは、カスハラを喫緊の課題として捉え、立ち向かう姿勢を明確にすることです。この法改正の目的は、従業員をカスハラから守ることにあるため、「我々はカスハラに毅然と立ち向かいます」といったメッセージを院長や理事長などの代表者が表明することが重要です。志高く医療介護業界に入ったものの、カスハラが原因で離職してしまう現状は、本人にとっても経営者にとっても非常に残念なことです。2025年4月の条例施行に向けて、事態はもはや待ったなしです。「4月までに」対策を完了できるよう、自院の最重要課題の1つとして準備していただきたいと思います。

【参照】厚生労働省『労働施策総合推進法の改正(パワハラ防止対策義務化)について』|厚生労働省
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/000756811.pdf
「経営者の味方になる」社労士としての使命を胸に
社労士資格を取得した時から現在に至るまで、「私は経営者の味方だ」というスタンスは変わりません。社会を見渡すと、実は経営者の味方は少ないと気づき、経営者を守ることが我々の使命だと感じています。より良い方向を考えている経営者様と真摯に向き合い、病院・介護施設の成長をサポートしていきます。 私はハラスメントや問題行動を起こす人がいた場合には、徹底的に対応します。その人のせいで疲弊している周りのスタッフを救うために「やらなければならない」、そのような正義感を持って仕事をしています。
「働く」に特化した法律のプロと共に
ハラスメントはもちろん、さまざまな問題に対して法律に基づいた対処法を的確かつ迅速にお伝えできることが、第三者として私にご依頼いただく最大のメリットだと感じています。私は通り一遍の対応ではなく、ご要望・ご意向をしっかりと確認した上でアドバイスを行うため、経営判断に役立てていただける点が強みです。労働関連の法律については絶対的な自信を持っていますので、医療機関・介護施設を確実にサポートすることが可能です。
東京と大阪を拠点に医療機関・介護施設からのご相談に対応していますが、組織規模をさらに拡大し、1000件以上のお客様に向き合う社労士法人を目指しています。また、社労士業務にとどまらず、人事評価やコンサルティングなど、人に関する業務も今後強化していく予定です。「お客様に寄り添う事務所を作る」というモットーを貫き、マイナビとの連携を大きな力にし、「日本一の社労士」と言っていただけるように努力を続けていきたいと思います。
労働環境整備/ハラスメント対策 専門家

社会保険労務士法人ベスト・パートナーズ
代表社員
米田 憲司専門家
その他「労働環境整備/ハラスメント対策」を得意とする専門家は複数います。お気軽にご相談ください。
関連する資料・ホワイトペーパー
White Paper