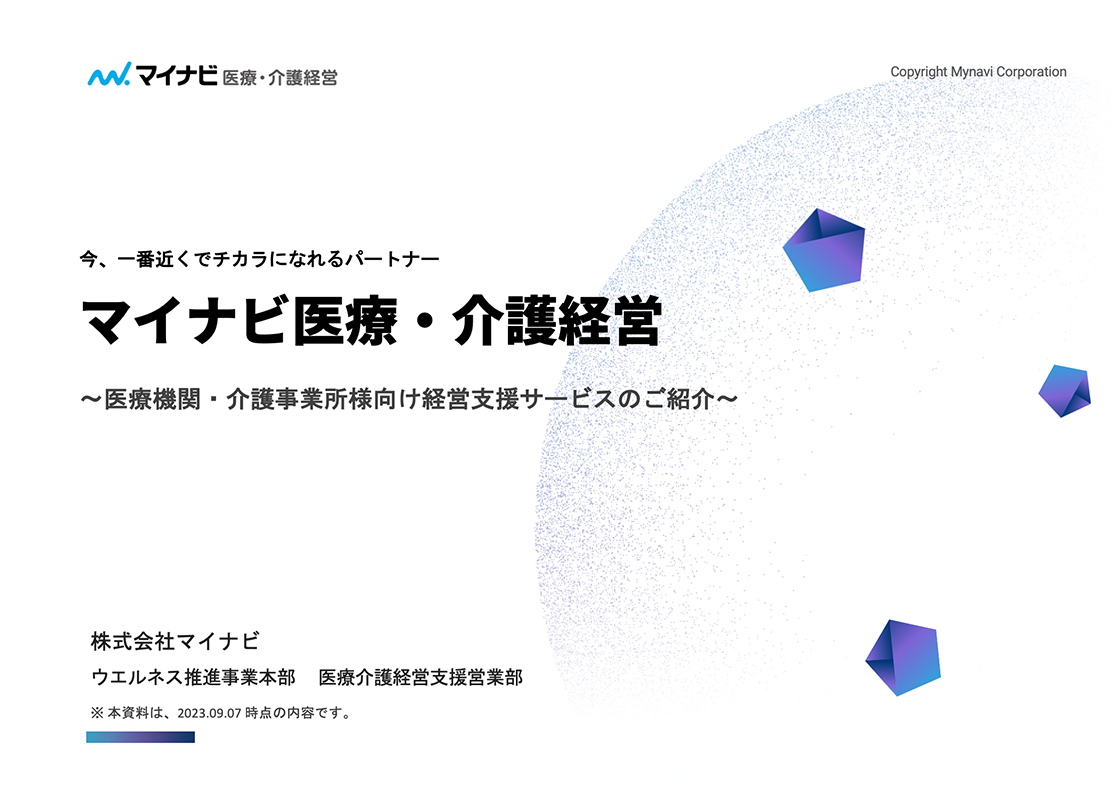このような課題を解決したい方へ
- 人事評価制度について取り組みたいが、なかなか時間が取れない
- 人事評価制度を効果的に活用し、職場環境改善をしたい
- 法人グループ全体で等級基準を統一したい

経営理念の実現に向けて欠かせない人事評価制度ーー医療機関・介護施設向け経営支援
マイナビ医療・介護経営の専門家: AIP経営労務合同会社 代表 大澤 範恭 氏
医療機関・介護施設でも耳にするようになった「人事評価制度」。その目的とゴールが何であるか、経営者として正しく理解した上で活用できているでしょうか。自院に合った人事評価制度、そして切っても切れない賃金制度を作成し活用することで、年々厳しさを増す採用力の向上と職員の能力向上が期待できます。35年に渡る厚生労働省での経験を活かし、現在は医業経営・医療労務管理アドバイザーとしてさまざまな医療機関・介護施設を支援する、大澤範恭専門家にお話を伺いました。

人事評価制度とは
「業績が上がらない」
「職員の退職が続く」
「頑張っているのに評価されずモチベーションが上がらない」
管理職や現場のスタッフからこんな声を聞きませんか?人事評価制度を導入しているにも関わらず・・・。
そもそも人事評価制度とは以下の目的で活用するものです。
- 半年~1年間職員の方の役割や能力を評価をして、その結果を踏まえて昇格・昇給の判断や人員配置する時の材料として使うもの
- 経営者側だけのメリットではなく、職員の能力向上、職員に対するエンゲージメントを高めるための一つのツール
人事評価をすることがゴールとなり、せっかくスタッフや管理職が時間をかけて評価したものが反映されないままとなっている病院・介護施設が少なくないようです。慢性的な人材不足、上限がある賃金体系、厳しい労働環境などの課題を抱える中で、職員のエンゲージメントを高め、働きたいと思える職場づくりを進めるためには、自院・自施設に適した人事評価制度を整えた上で、活用することが欠かせません。しかし、それを自力で行うには大きなエネルギーが必要になることから、外部支援を導入することでスムーズな運用が期待できます。
人事評価制度が注目される背景

一定の基準をもとにジャッジしていく人事評価制度は、小規模のクリニックから大学病院まで、すべての病院・介護施設に必要です。看護師の職能団体である日本看護協会が2019年に「看護師のキャリアと連動した賃金モデル~多様な働き方とやりがいを支える評価・処遇~」を発表し、給与体系・賃金体系について「複線型人事制度」「等級制度」を組み合わせた「賃金体系モデル」という協会としての考え方を示しました。頑張っている看護師が途中でリタイアしてしまうという現状を受けて、看護師1人1人の働きによって給料を決める人事評価をすることが求められているとの判断だと言えます。また、年々看護職の確保は難しくなってきており、他院との差別化や採用力の向上をはかるためにも必要だと、関心が強まってきているのだろうと思います。
【参照】公益社団法人日本看護協会『「病院で働く看護職の賃金のあり方」日本看護協会の提案』|公益社団法人日本看護協会
https://www.nurse.or.jp/nursing/shuroanzen/chingin/proposal/
人事評価制度をめぐる課題
経営者が立派なクレド(経営指針)を作ったものの、どのように評価し行動させるのかがわからず現場に落とし込めていないケースが目立ちます。人事評価の中に「経営理念の実現」という項目を入れ、クレドを行動に落とし込むことを行動基準に人事評価へ反映させれば、経営者の思いが具体的な行動に結びついていきます。そして経営計画も目標管理に落とし込むことで、同じ方向に向かって少しずつ近づいていくと考えています。目標管理は自分で目標を決めて、それを自分で達成し、自己評価して上司とすり合わせる、というプロセスが非常に大事ですし、上司のフィードバックによって能力が発揮されていくわけですから、そのプロセス抜きには語れません。
しかし、取り組もうと思っても病院の総務や事務長は日々の仕事に加え、診療報酬や監査への対応もあり、人事評価のことを考える時間的な余裕はなかなか持てません。本を読んでもそれを自院にどのように落とし込んだらいいかすぐにはわかりにくい現実があります。そんな時は第三者である私たちにご相談いただければ、ご状況と意見を聞いた上でフィードバックやご提案をすることができます。
第三者の介入で人事労務の課題解決をはかる

特に医師の働き方改革の場合は第三者が介入することで、提案を受け入れていただけることが多くあります。例えば、事務方の考えを聞き入れてもらえない場合でも、社会保険労務士やコンサルタントの資格を持った第三者が言うと、院長先生を含めて「話を聞いてみようか」となることも多く、それを運営に活用することができます。また、医師の働き方改革により、一層の労務管理が求められるようになりましたが、打刻しない医師に対して私から「きちんと打刻をしましょう」と話をすることで改善がはかれたケースもあります。
さらに、人事評価制度をコンサルティング会社経由で導入したものの、内容が緻密すぎて病院の職員や管理者の方々がうまく使いこなせないケースが多々あります。それにより形骸化してしまい、個人の目標設定や定性的な評価基準がないままに評価している状況が発生し、せっかく導入した人事評価制度をうまく活用できず、どうしたらいいのかと私に相談が寄せられます。その場合は経営者のご意向と病院の実情をよく見て、適切な運用に向けて微調整をはかり、正しい評価軸で人事評価できるように介入していきます。
賃金は、給与体系・人事評価と連携していますが、病院に併設して老健を設置するなど拠点を拡大していく場合は、病院・施設それぞれが、その時々の事情で賃金設計をしているため同じ法人内でも異なる状況が生じます。そのため、特に施設間の異動があると給与差が出始めることから、全体を職種別に統一し、法人内のどの病院・老健に配属されても、どこに異動しても同じ給与体系で評価されることを目指します。
また、人事評価の高さと昇給がまったく連携されておらず、その結果職員は何のためにやっているのかわからなくなってしまうという現状があります。そのため、人事評価と賃金の関係をうまく結び付け、合理的なものにしてほしいという相談が寄せられます。
今年の診療報酬改定でベースアップ評価料が創設されたので調べたところ、ほとんどの病院が「基本給とは別に一定の手当を払う」という方法を採用していました。歴史の長い病院ほど職務手当をはじめさまざまな手当を支給していますが、そのうえさらに、ベースアップ評価料の算定に伴い新たな手当を作ると、人事評価の結果に関わらず一定の手当を出す賃金の割合がどんどん上がってしまい、例えば、初任給のうち半分以上が定額で支給されることになりかねません。
令和8年度の診療報酬改定において、ベースアップ評価料がどうなるか、予断を許しませんが、今後とも医療人材の確保がますます困難になると見込まれますので、おそらく廃止されることはないだろうと思います。しかし、今回のように一律に加算を認めるのではなく、介護報酬における処遇改善加算のように、職員のエンゲージメントを高めたり、働きやすい職場にしたりする努力をしている病院には高い加点、そうでないところは低い加点というような傾向になっていくのではないかと予想しています。
そこで、令和8年度の診療報酬改定に備えて、この2年間で人事評価制度をブラッシュアップし、改定に対応できるような備えが必要です。そもそも人事評価制度は、職員の方を経営方針や経営理念に向かわせる方向づけをする機能、頑張っている職員とそうでない職員との公正な処遇、人材育成、この3つの機能があると思っていて、「今の人事評価制度はそれらの機能を果たしているか」という観点で点検することを勧めています。
医療介護現場のお悩みをこうして解決
過去、私が担当した事例ですが、人事評価制度はあるものの、看護部だけが一生懸命取り組み、事務部やコメディカルとは取り組み方のギャップが大きかったことから、看護部から「頑張っている職員に給料が上がる仕組みを徹底してほしい」という依頼があり、介入することになりました。
病院が目指してほしい職員像から考え始め、「成績」「能力」「勤務態度」3つの大きな要素から各管理職に具体的にどうなってほしいかを出してもらい、それを「等級定義書」として整理、フィードバックをして人事評価シートに落とし込みました。意見を出してもらった管理職の方からは「今までモヤモヤしていたものがすっきりしたと」いう感想をいただき、各現場で活用されています。
また、クレド(経営指針)はあるものの、人事評価で行動基準に結びついていない職員がいるのでどうしたらいいのか、という相談をクリニックの経営者から受けたことがありました。かつてそのクリニックでは、働かないと言われている職員も巻き込んで全職員でクレドを作ったと聞き、その職員と共にクレドを人事評価に落とし込む作業に取り掛かりました、何回かグループディスカッションに参加してもらい、その過程で「こうあるべき」と理解を得られ、クレドをふまえた行動に結びつくようになりました。
買収などで病院・老健が複数あり、さまざまな背景を持つ医療法人グループでは、法人本部で決めている人事評価制度があるものの、基準が各現場で設定されていたり、昇給昇格の基準が細かなところで異なる部分があったりしました。このような事例では人事評価の際に不公平感が出ないよう、職種別の等級基準をグループ内で統一することで賃金体系の課題を解決しました。
医師の働き方改革で厳しさを増す労務管理

2024年4月から勤務医への残業時間規制が年間960時間までに制限されましたが、全国の病院の9割は既に対応済であることから「医師の働き方改革は済んだ」と考えている病院が圧倒的多数を占めています。しかし、多くの病院は大学の医局等から医師を迎え入れており、派遣元の大学の医局等は年間1860時間の時間外労働を認められるために特例水準の指定を受けています。指定を受けた大学の医局等は、今後もずっとこの時間数が認められるわけではなく、2035年度までの12年間で900時間短くしていかなければならず、医師の派遣を取りやめざるを得なくなる可能性もあります。
一般社団法人全国医学部長病院長会議による調査では、「全国の大学病院の約半分が、医師の派遣を中止する、または削減する」と考えていることがわかりました。これは大学病院の問題ではなく、それを受け入れている中小規模病院も自分ごととして考えなければなりません。今後、状況は真綿で首を締めるように厳しくなっていくと予想しています。経営陣だけでなく、診療部長など医師の労務管理を担う立場にある方は、自分ごととして考える必要があると考えています。
また、長時間労働などを背景に、若い医師が外科を志望しない傾向があり、特に消化器外科の医師が数年前から減り続けている現状があります。そのことに気づいた日本消化器外科学会が勤務環境管理について学会として取り上げようとしています。令和4年に出た医師数のデータの中で外科医に注目すると、若年層や女性が離れている状況が明らかで、外科の未来が深刻な問題になっています。このままでは中小規模病院が医師を雇えなくなる可能性があり、そのことは経営に直結します。多くの医師が働きやすい環境を整えておかなければ、他の病院や他の業界にどんどん移ってしまい、経営が立ち行かなくなってしまうでしょう。
どうする?どうなる?賃金の課題
医療界に限らず、戦後の日本の多くの企業が職務遂行能力を評価して賃金を決める「職能給」を採用してきました。その結果、潜在能力も含めた能力を評価することはわかりにくく、結果として年功序列になっている現状がありました。
最近は特に労働力が潤沢ではないことから「ジョブ型雇用」を進めるべきだという動きが始まっています。その場合、職能給のように新入社員からずっと終身雇用前提のような設定では合いません。
厳しい財政事情の折から、診療報酬や介護報酬の大幅な引き上げは期待できない状況にあります。病院の収益の多くは診療報酬なので、収益が上がらないのに定期昇給をし続けることは困難です。そこで、ポストが空かなければ昇給させない役割給を採用すれば、人件費の自然膨張を防げますが、現実的には、定期昇給も無視できません。そこで、役割給と勤続給のハイブリッドとし、役割給の昇給ピッチ(1年間の引上げ額)を7割程度、勤続給の昇給ピッチ給を3割程度に抑える設計をしています。病院の中には「医療職棒給表」を真似ているところが多いですが、職能級であるためどんどん定期昇給していく必要があり継続が難しいと考えています。
適切な人事評価制度と賃金体系で安定した経営を
私は病院や介護に特化したアドバイスをしていますが、クライアントの要望によっては他業界や一般企業の人事に詳しい専門家の方に依頼した方がいい局面が出てくる可能性があります。そういうときにさまざまな職種を幅広くカバーしているマイナビ医療介護経営が介入することで最適な専門家をマッチングできるはずです。また、私とクライアントとの間に第三者的な立場でマイナビが介在することで、プロジェクトの進行管理が円滑に行われるというメリットがあると感じています。
15歳から64歳までの生産年齢人口は、今後2040年までの間に東京都の人口と同じ1300万人減少すると予測されています。その変化に対応すべく、医療福祉業界は働きがいやエンゲージメントを感じてもらえるような職場にすることが大きな要因になってきており、これから生き残るための重要なファクターとなります。今抱えている人事評価や賃金の課題を放置していたら、職員の定着や成長は望めないでしょう。今、見直すことで経営の安定化をはかり、地域医療確保を維持していただきたいと思います。
人事評価制度 専門家

AIP経営労務合同会社
代表
大澤 範恭専門家
その他「人事評価制度」を得意とする専門家は複数います。お気軽にご相談ください。
「人事評価制度」に関連する事例
Case Study
関連する資料・ホワイトペーパー
White Paper