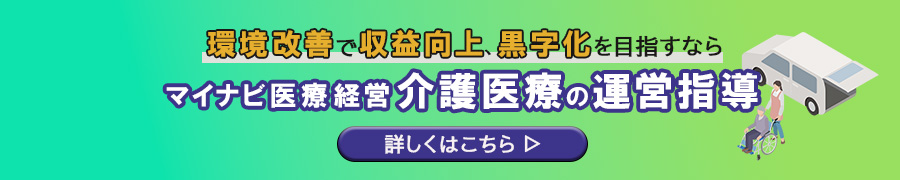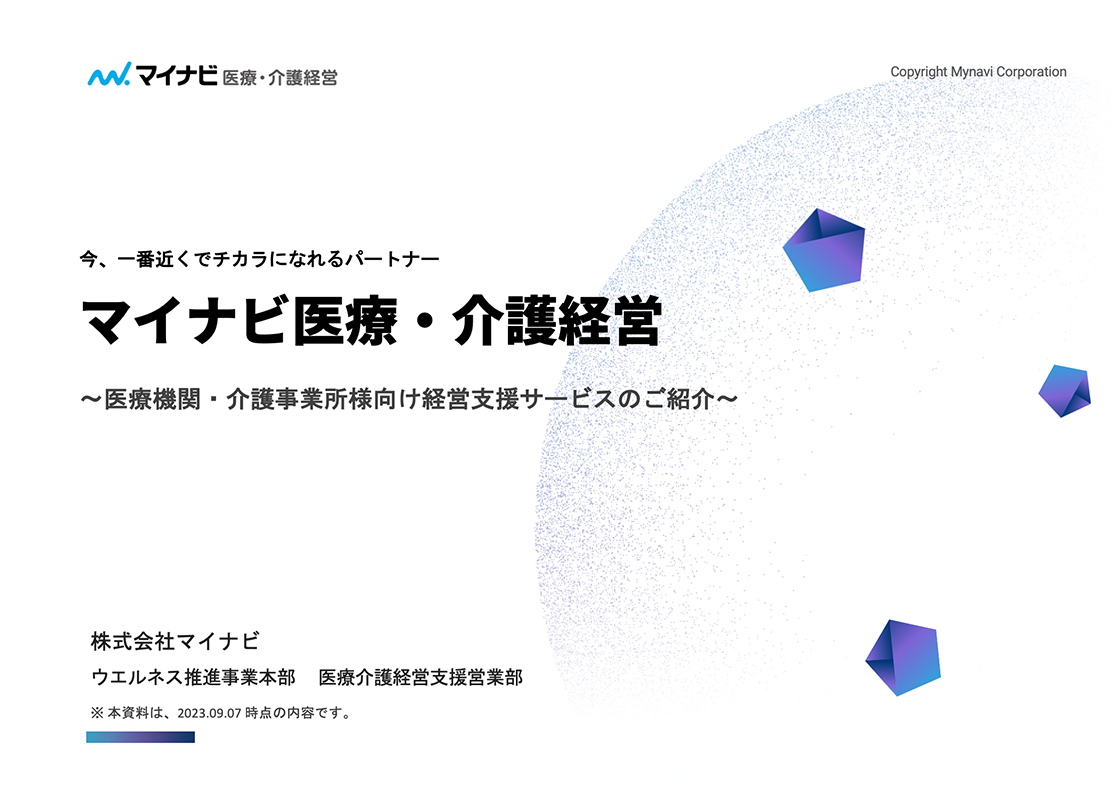このような課題を解決したい方へ
- 職員と利用者が笑顔で過ごせる施設を作りたい
- 人事評価制度を見直し、職員の定着率向上をはかりたい
- 介護環境改善により、黒字化を目指したい

介護現場に”環境”の視点をーー介護施設向けコンサルティング
マイナビ医療・介護経営の専門家: 株式会社IDO 介護部門ディレクター 山下 総司 氏
介護保険制度と共に発展を遂げてきた介護施設ですが、介護報酬の減額や物価上昇等に伴う経費の増額、職員確保・定着の困難などにより、その経営状況は穏やかではありません。一方で、外部の知見を積極的に取り入れ、経営の見直しを図ろうとする介護施設も増えています。自身も介護現場に職員・管理職として携わった経験をもとに、「空間の魔術師」として介護施設の「環境」に着目しさまざまな改革を実現してきた、山下総司専門家にお話を伺いました。

介護保険制度開始から24年、変化するコンサルティング
2000年に新しく介護保険制度が始まって以降、経営・人材育成等の構築の必要性が高まったことで、介護コンサルタントの需要が増加しました。これまでの相談内容は以下の時期的な変化をたどっています。
- 2000~2010年:施設の立ち上げ
- 2010~2020年:収益の上げ方、サービス内容、人材育成
- 2020年~:加算取得、経営の安定化
制度開始から24年が経ち、相談内容はさまざまに変化しており、最近では介護報酬が減収する中で、いかに加算などを取り漏れることなく収益を上げていくかが問われています。その結果、多くの施設が厳しい経営状況に陥っているように感じられます。
介護経営は「経営者」「職員」「利用者」という3つの歯車がうまく回ることで成立しますが、「経営者や職員が良い取り組みをしているものの、収益が全然出ていない」「サービスの質が悪い」という課題が出ている場合は、外部のサポートを得て経営の改善計画を策定するなど、具体的な行動を行い、経営状況を改善させる必要があります。
「環境はケア」これまでの介護実践がつながった日

僕がコンサルティングを始めて間もない頃、ある研修で「環境はケアだ」という言葉を聞き、「環境」という言葉が「尊厳」と同様に定義が大きく広域に解釈できることを知りました。介護における環境は、一般の人々がイメージする建物や温度といった物理的な要素だけでなく、ケアやサービスの質、さらには介護技術そのものも環境の一部であると理解するようになりました。
これまで僕がさまざまな介護現場で実践してきたことを振り返り調べてみると、2003~2004年に発表された環境づくりの指針である「PEAP」(認知症高齢者への環境支援のための指針)に繋がっていたことから、自分がやってきたことは環境というテーマと合致していたことがわかりました。それをきっかけに「介護環境」をキーワードに掲げ、さまざまな「環境」に課題を感じる法人に向けてコンサルティングを行ってきました。
環境は「ハード」「ソフト」「ルール」の3つに分類することができます。
ハード:建物の構造や間取り、仕事や行動の動線、整理・整頓
ソフト:人材配置や育成、介護実践のためのエビデンス
ルール:経営の方向性、締め切り、人事評価
「介護環境コンサルティング」は各施設に合わせて、この3つを整えることですが、具体的には、以下のことを言います。
- 主体的に動ける環境を作る:現状の施設に多い、利用者さんに「やってあげる」環境ではなく、利用者さんがコーヒーを飲みたいと思った時に自分で準備して飲める、施設で作ったバッグやお菓子を販売して収益を夏祭りなどのイベントで活用する
- 利用者さん一人一人が居心地のいい空間を作る:テーブルやテレビなどのレイアウトを工夫する
- 安定した経営基盤を構築する:人事評価を職員も役職者も納得のいくものに整え、その結果を給与に反映させる、利用者確保のために自ら営業する
しかし、この3つの要素をバランスよく保ち、実践するための努力や方法が施設内に不足していることが多い現状があります。
経営改善に併走し、収支を4300万円プラスに
過去に経営改善を目的に介入した事例では、複数の介護施設を経営する法人全体で約1800万円あった赤字を、3年以内に約2300万円の黒字に転換しました。また、小規模のデイサービスでは、月額80万円の赤字を出していたところ、約1年の介入で月額40~50万円の黒字に戻したケースもあります。両者に共通しているのは、黒字化のために法人全体で事業内容・広報活動・職員教育・評価・人事などに総合的に介入し、改善の必要性をアドバイスし、法人側がそれを確実に実行したことです。
法人のケースでは、すべての事業所が赤字経営という現状で、そこから黒字に転換するため、デイサービスやショートステイなど各事業所の特徴を洗い出し、サービス内容と経営状況を精査しました。また、収入や支出について具体的な数値を提示し「このままでは数年後には社会福祉法人として存在できなくなる」という事実を職員全員に説明し、危機感を伝え、改善に前向きになってもらうことにも努めました。
当時、デイサービスの利用者さんが平均1日20人のところに職員が根拠なく11人も配置されている状況でした。本来は利用者数などのデータに基づいて人員配置を行う必要があります。そこで、根拠となるデータを示すことで、適切な人員配置へと改善を図りました。また、長く勤めている方は、当然基本給が上がっていきますが、頑張って仕事をしてくださる方がいる一方で、中には怠惰な職員も存在します。やる気の低い職員がデイサービスに集まるという状況を改善するため、経営指標と人事評価を照らし合わせて適正な人員配置を推奨しました。
このような環境を整えた上で、事業の適正化を目指し、売り上げを増やすことへとシフトした結果、当時稼働率が50%を下回っていたデイサービスが90%近くに、稼働率が60%を下回っていたショートステイは96%までに回復しました。
第三者によるヒアリングが現場を変えるきっかけに

このような課題を抱える事業所に僕のような第三者が入るメリットはいくつかあります。例えば人事権を持たないため利害関係がなく、職員の方たちから忌憚のない意見を聞くことができること。また、全国のさまざまな法人で取り組んでいる具体的な事例を示し、この方法を取り入れればどのような変化が起こるかを伝えられることです。
僕の場合、給食を作る方たちやドライバーなどを含む全職種を対象に一対一のヒアリングを必ず実施しています。最初は初対面であるため「山下さんに言って大丈夫なのか」と警戒されることもありますが「言ってくれればこちらはアクションを起こす」と伝えて少しずつ関係性を築き、2~3回ヒアリングしていく間に現場に変化が出始めると、職員から話していただけることが増えます。文章にすると短いですが、そこに到達するまでに1年くらいかかります。
基本的に月に1~2回訪問し、ポイントを絞って現場の職員からヒアリングし「経営者から顕在化している問題を解決してほしい」「やる気がある職員をもっと伸ばしてほしい」など、組織課題を聞いた上で、解決に向けた方法を検討していきます。解決には少なくとも3年はかかります。マイナス状態の収支をある程度プラスにするまでが3年。そこから売り上げを増大させたり、職員を成長させるためにはさらに1~2年かかるため、施設の要望を聞きながら介入期間を決めていきます。
役職者も職員もハッピー「3段階人事評価」のススメ
最近は人事評価を活用する施設が増えていますが、「職員が自己評価できない」「役職者が適切に部下を評価できない」という声をよく耳にします。その背景には、一般的に出回っている評価表を介護現場でも活用している状況があり、項目がまったくフィットしていなかったり、項目数が多く、使いにくいという問題があります。このような場合、僕が作成した3段階評価表を提案し、それに変更することで自己評価を可能にする環境へと改善していきます。
3段階評価では「〇:できる」「△:自信がない」「✕:できない」という項目に分類します。5段階評価の場合、控えめな職員は上の人の評価を気にするので「5をつけたら自信過剰だと思われるから4にしておこう」と考えたり、自己肯定感が低い職員は3と2しかつけなかったりする調整が入ってしまいます。このような自己評価では、役職者が適切な評価をすることは難しいため、職員も役職者も評価しやすい内容にすることが重要だと考えています。
基本的に、評価は本来役職者が行うものですが、僕の評価は役職者も現場の職員もお互いがいいところ・悪いところが言えるような仕組みにしています。例えば、デイサービスの職員が10人いるとしたら、お互いが自己評価を見て〇や△をつけた理由についてディスカッションし、評価を下げる必要がある場合は「こういうところを直してくれたら〇だと思います」などと伝えるようにしています。現場で働く職員同士が一番お互いの仕事ぶりを見ていますので、役職者だけが評価するのではなく、全員が評価し合い、その後役職者が意見をまとめ、面談時にフィードバックを行います。そうすることで、役職者は部下を評価するプレッシャーが軽減されます。また、評価は匿名式で自分の名前出さないように行うので、職員も包み隠さずに意見を述べることができます。それが僕の評価表の特徴です。職員からの反発もありますが、日々の貢献が適切に評価される仕組みが最も公平であることを伝え、理解を得ています。
職員に自信をつける評価表に

5段階評価がスタンダードな環境では、人の目を気にした評価になってしまうと感じていました。3段階評価にすることで「できる」という評価をつける項目が増え、職員は自信を持つことができます。また、悶々とした気持ちを抱え込まずに言いたいことを言える環境を整えることで、離職率を下げる効果もありました。
また、適切な人事評価を給料に反映することも重要です。例えば、夏の賞与が2ヶ月分として、そのうち0.6~0.8ヶ月分程度はこの評価表に左右されるくらい影響が出ると言うと皆さん努力しますし、自己評価にも真剣に取り組むようになります。
5段階評価の時は控えめな自己評価をしていた職員も、3段階評価になると「できる」をつけるように変化していました。その理由について尋ねると「できていることはきちんと〇をつけて評価し、ボーナスに反映させたい」との声が聞かれ、自分と向き合い適切な評価ができるような新たな環境が生まれていました。
もっと多くの介護施設に「介護環境」を取り入れた介護ケアを広めたい
これまで多くの研修やセミナーを通して「介護環境」の重要性を伝え、アドバイスを行ってきました。しかし、僕個人の発信だけでは届けられないクライアントがまだ多く存在します。幅広いニーズをとらえ、それらを解決できる多くの専門家を抱えているマイナビ医療・介護経営と共に歩むことで、より多くの介護施設の課題解決を図っていきたいと考えています。
経営に携わるほど人材育成の難しさを感じていますので、今後は介護現場における採用と定着を強化していきたいと考えています。各施設の定着に向けた取り組みを尊重しつつ、経営者が安心でき、現場の職員が不満を感じず、利用者さんが満足するような環境を構築することを目指しています。
また、介護だけにとどまらず、今後は障害者支援の分野にも活動を広げていきたいと考えています。就労B(就労継続支援B型)における賃金増額の方法や、どのような仕事に取り組むべきかなど考えることに非常に興味があるので、勉強や情報収集を重ねた上で活動を展開していきたいと考えています。
医療も介護も単価が下がることが予想される中で、正しい選択・固定概念にとらわれない人材育成・幅広い採用を実践できるよう、頼れるものには頼ることが重要だと思います。自施設ですべてに対応できることが理想ですが、足りない部分を補うという姿勢で、安定した経営を目指し続け、より良い施設に成長していただきたいと考えております。
介護医療コンサルティング 専門家

株式会社IDO
介護部門ディレクター
山下 総司専門家
その他「介護医療コンサルティング」を得意とする専門家は複数います。お気軽にご相談ください。
関連する資料・ホワイトペーパー
White Paper