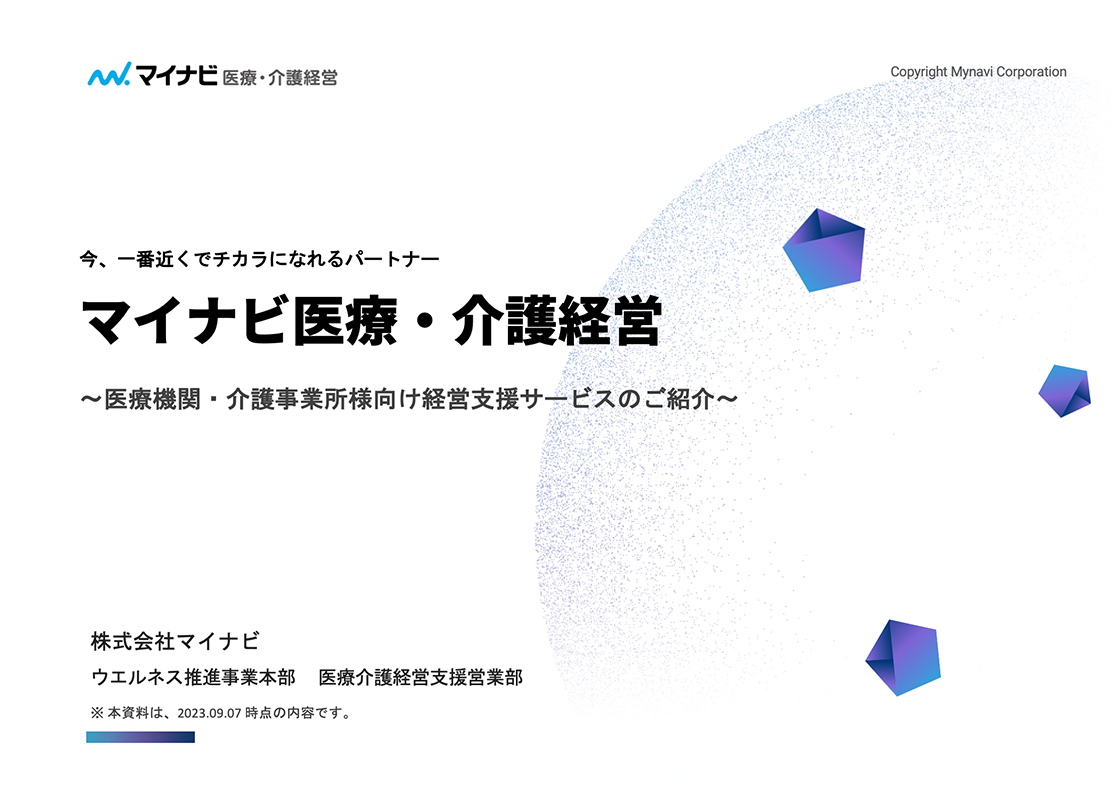このような課題を解決したい方へ
- 算定方法の適正チェックを行い、収益を上げたい
- 第三者の視点により課題を見つけ、改善に向けて行動したい
- 組織力向上による収益増加を目指したい

診療報酬・介護報酬・調剤報酬業務が経営・組織運営を映し出すーー診療報酬・介護報酬のアドバイスによる経営支援
マイナビ医療・介護経営の専門家: N・K 氏
毎月のレセプト請求に返戻対応への対策。そして2年に1度の診療報酬改定。医療機関・介護施設の収入の多くは保険者からの支払いが占めており、いかに漏れなく適切な請求・改定対応をするかが経営に大きな影響を及ぼします。複雑化する診療・調剤・介護報酬の中で私たちはどのような対応をすべきなのでしょうか。長年診療・介護・調剤報酬業務に携わるスペシャリスト、N・K専門家に、報酬業務を考える上で必要な視点についてお話を伺いました。

診療報酬・介護報酬支援とは
「正しいと思ってレセプト請求したのになぜ査定されたのか」
「新設された加算を算定したいがどのように準備すればいいのか」
日々の請求業務や今後の改定への対応において、事務スタッフや事務長の悩みは尽きることなく、それに加え、電子化により診療報酬請求の仕組みが複雑になりました。しかし、それを理解できる人材が不足していることから、サポートが求められています。「電子化したから知識は不要」という風評が飛び交っていますが、複雑になればなるほど仕組みを理解する必要があります。また、最近は電子カルテの導入によりレセプト請求が自動化されつつありますが、システムによっては手入力や目視で確認しなければならず、日常業務から未来に向けた準備まで、幅広く対応するための支援が必要とされています。
業界別に見ると、病院や薬局ではICTが発達している傾向にある一方で、介護の世界では紙でのやりとりが多く、ICTがなかなか進んでいないことが現状です。また、介護報酬はコード化されていることから「介護報酬請求は簡単だ」とする風潮があり、専門の事務スタッフの整備ができていないことも課題で、ここにも外部支援が必要です。
専門家のアドバイスが導く2つの課題解決

- 自院・自施設での算定方法の適正チェック
「自院の査定率が平均よりも下回っているからこれでよいのか」
「もっと算定できる加算はないだろうか」
「現状の算定で改善すべき点はないだろうか」
「この電子カルテは市場の適正価格で納入されているのか」
こうしたことを第三者の視点で検討することは、収益を上げるためにも重要です。短期間でも介入してもらうことで課題解決に近づけられます。黒字であったとしてもそれが継続できる組織なのか、すぐに赤字に陥ってしまうのかを確認し、組織力を確認しておくことが大切です。 - 組織形成レベルを他者の視点で確認
今後、病院機能評価やISOの審査を受けることが必須になると予測しています。審査では組織形成できているかどうかが見られ、特に病院機能評価は一般企業をベースにしていることから企業並みの組織が求められています。そのため、専門家を有効活用し課題を明らかにするとスムーズに受審が進むのではないでしょうか。
診療報酬をめぐる課題解決に向けて必要な第三者の目
医療機関・介護施設の多くは、他院・他施設の経営状況や査定の割合などを知る機会はなく、評価の指標を得にくい状況です。そこで、さまざまな医療機関・介護施設に介入している外部専門家が関わり、第三者の視点で評価することで問題に気づき、改善に向けた行動をおこすことができます。ある病院から“外の世界を知らない自分たちの意見が適切なのかわからないため、第三者の目で見てもらいたい。”という依頼がありました。診療報酬は軽微な修正のみでしたが、経理部、薬剤部などすべての部署をまわって現状分析をしたのち、組織課題や人材育成の問題点を抽出し改善案を提案したところ、大きく収益改善を図ることができました。単に診療報酬だけを見るのではなく、院内全体の改善を働きかけ収益増加を目指す、これこそ本当の専門家の介在価値だと考えています。
また、今は加算が取れる・取れないという世界に変化し、加算も「上位加算」「下位加算」に分かれるなど複雑化しています。それに伴い、加算Aを算定したら加算Bも算定できるが、実現させるためには院内体制がどこまでできているのかを確認し介入する、そのような支援が多くなってきました。今、入院の診療報酬は「どこまで加算が算定できるか」が課題ですが、残念ながらその体制が整えられていない医療機関が多くあり、支援を必要としています。
代表的な例は「食堂加算」です。これまで私が見てきた医療機関のほぼ100%が算定できていません。これはとてもシンプルな加算ですが、病棟構造が複雑になってきており、再編時等に確認せず、以前から運用しているものをそのまま継続して請求してしまっている背景があります。病床数が少なくても1日50円の加算は、1年で考えるとかなりの額になることがわかります。
収益増加を目指す際に問われるのは組織力

また、診療報酬の問題は事務部門だけで解決できるものではなく、他職種・他部門との連携が欠かせません。その要となるのは事務スタッフです。例えば、現状算定している加算を取りたいものの必要事項がカルテに未入力だったり、なぜこの薬を処方したのかを確認したかったり、病名の記載漏れを指摘したり。こうしたことを事務スタッフがパイプ役となり医師・コメディカルと気兼ねなく話し合える関係性が重要ですが、一朝一夕に成し得るものではなく、日頃からの風通しのよいコミュニケーションが必要です。
つまり、加算を算定できるかどうか以前の、根底である組織作りができていなければ、いくら私が「この加算が算定できます」とアドバイスしても実現は難しいでしょう。マイナス改定と言われている中で、黒字経営を維持している医療機関・介護施設はたくさんあります。そのような組織は多職種間でのコミュニケーションが活発で、また、次の改定でどこにメスが入るかを予測し対策をたてています。
多くの医療機関・介護施設は改定内容がわかってから慌てて対応に走りますが、次にどこが改定されるか、先読みすることができる専門家を活用することで、事前準備が可能になります。今回の改定で大幅に修正された「特定疾患療養管理」や「薬剤情報提供」は、私が以前から「今後間違いなく修正される」と予測していたことの1つで、そのようなアドバイスを聞き入れて体制づくりを実行できるかどうかが経営の明暗を分けると考えています。
また、自分たちができることとして、改定前に開催されるセミナー等に参加し、次回の改定の全体像をつかんでおくことが挙げられます。例えば、厚労省が開催する報酬改定セミナーは、改定の全体像を話すだけだから必要ないと思われがちですが、背景にどのような意図があり改定に至ったのかという流れを確認でき、事務スタッフに必要な俯瞰力を身に着けられることから、直接自院に関係ない内容であっても参加することを勧めています。
時代の変化に適応するために人材育成と顧客満足に注力
時代の変化に伴って現場にも変化が起こっています。現在は電子化に転換する過渡期で、紙も電子媒体も活用する必要があり、電子化と言いながらまだ手作業のところも多くあります。紙からwebへ、そしてAIとの協働という未来に向け、今後どこまでAIが入り込んでくるかを想定した業務内容の構築、職員の育成が急がれます。これからさらに事務の業務は広がっていくことが予想されており、管理職だけでなくスタッフ1人1人が時代の変化に敏感になり適応していくことが求められています。さらに、診療報酬改定も2年に1回ではなくなってきているため、事務部門の苦手分野である情報収集力を獲得してそこに向き合える組織力をつけていくことも必要です。
一方で「窓口に来た方すべてがお客様(=顧客)」「各医療機関・介護施設の評判を高めてくれるのがお客様(=顧客)」という考えを持ち、患者さまはもちろん、医師・コメディカルなどすべての職員、出入り業者など、病院・施設経営に関係するすべての人たちを大切にすることで初めて経営がうまくいくケースをみてきました。これは時代が変わったとしても不変であり、ここをブレることなく継続できる組織は、経営面でも強くあり続けるでしょう。

マイナビ医療・介護経営と共に確実な診療報酬と収益確保に向けた前進を
診療報酬は日に日に厳しくなり、医療機関・介護施設が廃業する時代になりました。診療報酬を考える上で保険点数だけをみるのではなく、患者さまや職員1人1人を大事にすることで、自院の信頼度向上につながり、安定した経営をもたらします。そのようなアドバイスができる専門家と共に今後の診療報酬の動向を先読みしつつ、一つ一つの医療機関・介護施設とていねいに向き合いながら、課題解決に向けて常に気を配り進めてくれるマイナビ医療・介護経営と共に、三者で歩むことで、収益確保に邁進していただきたいと思います。私たちは皆さまの応援団です。
診療報酬/加算 専門家

N・K専門家
その他「診療報酬/加算」を得意とする専門家は複数います。お気軽にご相談ください。
関連する資料・ホワイトペーパー
White Paper