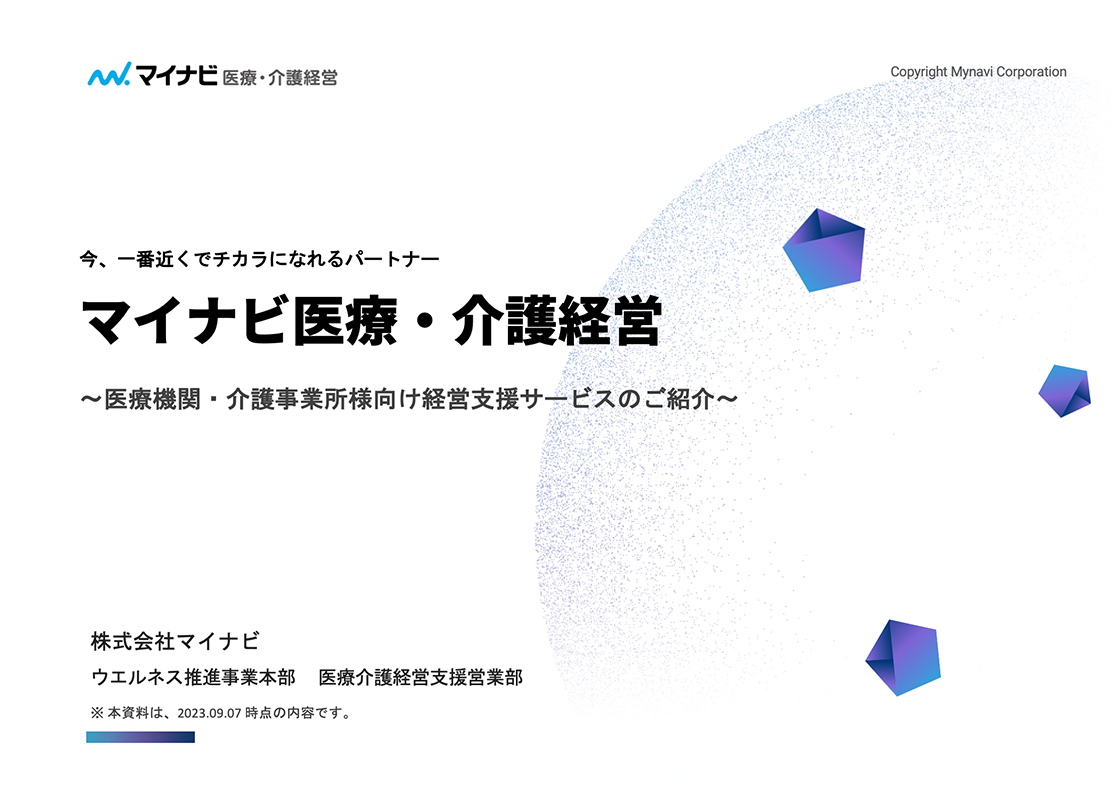このような課題を解決したい方へ
- 自施設における「人事」に課題を感じている
- スタッフのメンタルヘルス向上と虐待防止で、安心の職場作りがしたい
- 外部の視点から自施設の課題を把握し、解決に向け取り組みたい

高齢者福祉における「虐待予防」の現在
マイナビ医療・介護経営の登録専門家:グスタフ・ストランデル氏/高橋 公子氏
高齢者虐待の件数が年々増加傾向にあることは、皆さんご存じでしょう。厚生労働省の調査※にもそれは表れており、例えば令和5年度の養介護施設従事者などによる虐待件数は1,123件で、前年度より267件増加しています。
【参照】厚生労働省『令和5年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果』|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48003.html
高齢者福祉をテーマにスウェーデンと日本で調査・研究を行い、現在は両国の福祉の架け橋としても活動するグスタフ・ストランデル専門家(以下、グスタフ氏)はこう話します。
「虐待件数の増加は、早期発見の意識が現場に浸透していること、そしてチェック機能が有効に働いていることの表れだとも言えます。介護現場が虐待ばかり起こしていると印象付けるような一部マスコミの報道は正確性に欠けますし、この業界で奮闘する人々の心を傷つけるものでしょう。冷静な態度で有効性のある施策を打つことが大切です」(グスタフ氏)
また、公私共にグスタフ氏のパートナーであり、日本で介護施設長を務めながら世界の介護業界にも活動の幅を広げている高橋公子専門家(以下、公子氏)は、次のように指摘します。
「完璧な介護をしなければという思いが、虐待の芽になってしまうこともあります。こうした事態を防ぐために、管理者ができることをしっかりと考えていきましょう」(公子氏)
日本の介護業界の実態を熟知し、虐待防止についても効果的な取り組みを模索し続けてきた両氏に、詳しくお話を伺います。

まずは「現場を追い詰めないこと」が大原則
-
公子氏
-
介護施設の現場では、相手を思っての行為が行き過ぎて、虐待に該当してしまう――というケースがあります。例えば、部屋の外に出ようとする利用者さんに対して「危ないから」と座っていることを強要し、それが必要以上の身体拘束につながるといったことです。また、着替えを嫌がる利用者さんに、清潔でいてほしいという思いから、体を押さえつけて服を脱がせるようなことも考えられるでしょう。
こうした行為の背景には、利用者家族からのプレッシャーが少なからず存在すると感じます。利用者家族の中には「施設では何でも完璧にこなしてくれる」と考え、非常に高い理想を求める方もいます。しかし、転倒や転落、窒息、感染症などのリスクを完全にゼロにすることは現実的でありません。私が運営する施設のように、当事者の自由や思いを重視する方針であればなおさらです。組織として介護現場のリスクについてどのように考えているか、方針をしっかりと契約時に説明・納得してもらうことが、利用者家族からの過大な要求を防ぎ、現場を追い詰めないことにつながると思います。
また、実際にサービス開始してからも、利用者家族とのコミュニケーションを積極的に図りましょう。できるだけ頻繁に施設を訪れ、支援の現場を見てもらうことが肝心です。自分たちがどれだけの熱意を持って利用者さんに接しているか、直接見て理解してもらうことが、無理のないケアに結び付くはずです。
スタッフの心に響く虐待予防研修のヒント

それでは、虐待予防についてスタッフに学んでもらうには、どのような方法が有効なのでしょうか。お二人が実践してきたポイントを伺います。
- かつての介護現場を伝える
-
グスタフ氏
-
私が日本の介護現場を初めて見たのは、介護保険制度が施行される以前のことです。その時、見学した施設では「一部屋に何人もの高齢者を詰め込む」「勝手に動かないよう縛る」「排泄ケアが不十分で褥瘡ができやすい」といった状態が決して珍しくありませんでした。当時の常識は今と異なりますし、状況的にやむを得ない部分も大きかったわけですが、現在の基準で見れば虐待と思われることも……。当事者が感じた苦しみを風化させないためにも、こうした「歴史」を今に伝えることは重要だと感じます。そこで私は、過去の介護現場について写真やイラストなども交えながら解説し、そこからどのように改善が重ねられ、虐待防止の理念が整えられてきたかを研修で伝えています。
-
- 「尊厳」について考える
-
グスタフ氏
-
当事者視点の考え方が浸透してきたことも、日本の介護現場の大きな変化の一つです。教科書的な虐待予防の知識を説明するにとどまらず、上記のような歴史を伝えた上で「人間の尊厳とは何だろう?」と各自に考えてもらうことも、有効な教育法だと言えるでしょう。「尊厳」はこの業界でよく耳にする言葉ですが、それが具体的に何を意味するかは人によって異なるものです。こちらが決めた定義を教えるのではなく、「もし自分が当事者になったらどんなケアを望むだろう?」と自己決定についてリアリティーを持って考えてもらったり、ディスカッションを通して多様な意見を共有したりすることが、スタッフの心を動かすはず。理論と実践の両方が伴う、より深い学びにつながります。
-
- 利用者自身をよく知る
-
公子氏
-
「尊厳」や「自己決定」という言葉だけを抽象的に捉えていても、現場の業務に落とし込むのは難しいですよね。そこで、いわゆる事例検討のような機会を意識的に設けることも、虐待予防につながると考えます。私が運営する施設では、研修の一環として、一人の利用者さんをじっくりと研究する時間を設けています。これまでどのような人生を送ってきたか、何を大切にしていているのかといったことを知り、「この人にとって幸せに暮らせる環境とは?」を検討するわけです。知識が深まれば見え方も異なってくる――という事実は、旅行前に下調べをするかどうかで観光地の見え方が変わることにも似ています。この研修では、特にケアが難しい利用者さんをピックアップすることが大事。気難しく本音が見えにくかったり、難易度の高い介助が必要だったりする人の方が、虐待につながるリスクも高くなりやすいからです。逆に言えば、こうした利用者さんにも適切なサービスを提供できることが、プロの証と表現できるかもしれません。
-
虐待にも大いに影響する「人事」の在り方
-
グスタフ氏
-
介護施設経営の要は「人事」であり、これがうまく展開できている組織では、虐待の問題も起こりにくい(あるいは深刻化しにくい)傾向があります。ここで言う人事とは、上記に挙げたような研修はもちろん、理念の浸透、ケア手法の教育、チームワークの形成、適切な人員配置などを含みます。これらを通して「自分の取り組んでいる仕事には意義がある」と感じながらスタッフが働けることが、何より重要なのです。虐待やそれに類する問題が何度も起きる場合は、「人事がうまくいっていないのでは?」という観点で抜本的な改革を図る必要があるでしょう。そうした点についても、私たちがお手伝いできることは多いと思います。
-
公子氏
-
介護施設に限らずどのような組織でも「人事がすべて」であることに変わりなく、掲げられた方針に管理者が賛同しているか、そこで働くことにスタッフが幸せを感じているかどうかが重要です。だからこそ私たちが大切にしているのは「働くウェルビーイング、働くパーパス」という言葉。ウェルビーイングとは、身体的・精神的・社会的に良好な状態であることです。仕事を通してワクワクできる、やる気に満ち溢れるという状況をつくることがポイント。これを働く人が実感できてこそ、利用者さんのウェルビーイングも実現できるのではないでしょうか。

-
「虐待かも?」と思った時の組織的対応とは
-
グスタフ氏
-
虐待案件の多くは「疑い」から始まります。私が以前に経営していた法人でも、ある利用者さんに違和感のある傷がついているという、虐待を疑うような報告が上がってきたことがありました。こうした時、注意しなければならないのが「虐待の疑いを持たれたスタッフ」への対応です。疑われた時点から、その人が精神的に非常につらい思いをすることは間違いありません。いろいろな考え方があるかと思いますが、やってしまったことが証明されるまでは「推定無罪」として扱い、経営者や管理者は当該スタッフを守る方向性で対応すべきだと私は考えます(もちろん、実際に虐待をしていた事実が判明した場合には、厳しい対処が必要になるでしょう)。
また、本当に虐待が発生したかどうかを突き止めることは、想像以上に難しいというのが私の実感です。事実確認のために委員会を設置し、冷静かつ客観的な視点で調査・分析することが求められます。大変デリケートで難しい問題だからこそ、組織的対応の在り方に悩んだ時は、私たちのような専門家に相談することも考えてほしいと思います。なお、私が経験したケースでは、疑いを持たれたスタッフを最終的に潔白であると判断したものの、本人や周囲の心情面に配慮して人事異動を行うことで収束させました。
スタッフが犠牲にならない介護現場をつくるために

-
公子氏
-
介護業界では、自施設の中ですべてを完結しようとして、視野が狭くなりがちな傾向があります。一生懸命やっていることが実は時代遅れだった……なんてこともあり得るからこそ、外部の視点を入れることは重要です。業界内だけでなく異業種にも、日本だけでなく海外にも積極的に目を向けてほしいと思います。そうした手段の一つとして、マイナビ医療・介護経営のようなサービスを活用することも一案ではないでしょうか。
-
グスタフ氏
-
「虐待」とは非常に強い言葉であると同時に、幅広い概念を含みます。故意に攻撃するような行為だけでなく、その人を思ってやったことが結果的に該当することもありますからね。悪意があるようなケースは別として、同じことが繰り返されないよう互いに学び、知見を共有する姿勢が大切で、個人を責めないことが基本ではないでしょうか。スタッフのメンタルヘルスにも目を向けながら、自己犠牲を強いるような現場にならないよう配慮することが、結果的に虐待を減らすことにつながると信じています。
-
虐待防止研修 専門家

グスタフ・ストランデル/高橋 公子 専門家
その他「虐待防止研修」を得意とする専門家は複数います。お気軽にご相談ください。
関連する資料・ホワイトペーパー
White Paper