
看護助手の早期退職をきっかけに、院内改革に着手
目次
課題と解決とその効果
課題
- 教育の際にマニュアルがなく、人事評価が曖昧で職員の成長イメージに課題があった
- 組織の成長に、制度が追い付いていなかった
解決策
- 必要とされる技能を言語化・標準化する「マニュアル」を作成
- 西崎内科医院オリジナルの「人事評価制度」を確立
その後の効果
- 「マニュアル」作成を通し、AI 活用など他の業務の効率化にもつながった
- 職員同士で意見を出し合い、自発的学習が促進された
- マニュアルと連動した客観的かつ公平な人事評価が可能になった
マイナビ医療・介護経営で専門家を活用する組織には、一体どのような変化が起きるのでしょうか。ここでは、実際に経営課題の改善に向けて取り組んだ法人の皆さんに、実感できたメリットについて詳しく伺います。今回登場していただくのは、西崎内科医院の西崎哲一先生(院長)、岩下順一さん(事務長)、そして同院のパートナーとして活動したマイナビ医療・介護経営登録の専門家、橋本Bob宏昭さんです。
看護助手の早期退職をきっかけに、院内改革に着手
-
西崎 哲一先生
-
若い頃から透析医療に携わっていたので、この領域に強い医療機関を岡山の地につくりたいという思いで、1977年に西崎内科医院を開業しました。透析医療は黎明期に比べると格段にレベルが向上していますが、それでも現状では「完治」をめざすことはできません。慢性腎不全(腎臓病末期)の患者さんは生涯にわたって治療を続ける必要があり、だからこそQOL向上の一助となり、より楽しい人生を送れるようサポートしたいと考えています。そのために欠かせないのが、仲間の存在です。透析患者さんを医師1人だけで支えることはできず、看護師、臨床工学技士、臨床検査技師、管理栄養士といった多職種の力が絶対に必要となります。そうした思いもあり、院内にいる皆と協力し合えるよう、家族のような信頼関係の構築を心がけてきました。

-
岩下 順一さん
-
西崎院長が職員とのコミュニケーションを重視していること、そして職員も西崎院長を慕っていることを、私自身も実感してきました。例えば、忙しい外来の時間が一区切りした時、「君たちがいてくれてよかった」「体調は大丈夫?」といった一声を、時にはユーモアを交えながら、看護師や受付担当などに必ずと言っていいほど伝えています。皆で一緒に頑張ろうという思いが組織に浸透し、チーム一丸となって診療に当たれている感覚です。実際に、定着率も非常に高い状態でした。ところが数年前、ある1人の看護助手の方が、採用後に早期退職されることに。これが、当院の運営を見直す大きなきっかけとなりました。
-
西崎 哲一先生
-
一人ひとりと向き合い、良好な関係が築けていると思っていたので、理由も分からず突然退職されたことはショックでしたね。私には言いにくい困り事があったのかもしれないと心配になり、岩下事務長やマイナビの担当者に事情を聞いてもらうことに。すると、「業務を教えてもらう際にマニュアルなどがなく、人事評価制度もあいまいで、どのように成長していくかイメージが持てなかった」といった声が出てきたのです。20人くらいの小さな規模感でスタートした当院ですが、現在では約60人の職員を抱える組織に成長し、制度面の改革が必要になってきたのだと感じました。
-
岩下 順一さん
-
本件を契機にいろいろと反省点を洗い出し、マイナビの担当者とも相談する中で、「マイナビ医療・介護経営」というサービスでプロフェッショナル人材である専門家の派遣を受けることになりました。そして1年半ほど前にご紹介いただいたのが、業務改善や人事戦略などに造詣の深い、橋本Bob宏昭さんだったのです。
外部の専門家と練り上げたマニュアルが職員の成長に寄与
-
橋本 Bob宏昭さん(医療・介護経営の専門家)
-
私たち外部の専門家がするべきことは、特定のやり方を押し付けるのではなく、組織やそこで働く職員の魅力・強みを引き出し「伴走」することだと思っています。当然のことながら、改革に必要な力を持っているのは、現場で奮闘されている皆さんですからね。これまで数百、数千という数の組織を見てきたので、これらの知見をもとに各院への提案をアレンジできることが私の強みだと自負しています。中でも、西崎内科医院のような「愛ある組織」に関われたことには、非常にやりがいを感じました。今回、具体的に取り組んだことの一つがマニュアル作成です。小中規模の医療機関にはマニュアルが存在しないこともまだまだ多いですが、「何となく経験則で教える」からステップアップし、必要とされる技能を言語化・標準化することは非常に重要です。

-
西崎 哲一先生
-
現在、透析患者さんに対しての処置の段取り、厨房スタッフの一日の流れなど、院内のあらゆる業務をマニュアルに落とし込んでいます。標準化を図る中で、よりよい動き方や手順などが明確になっていくことを実感する日々です。なお、マニュアルの一部は動画化も推進。ちょっとした隙間時間にも気軽に見られるよう、例えば透析開始操作の手技などを動画撮影し始めているところです。さらに、橋本顧問のアドバイスを受けて、AIによるプログラム化にも挑戦。AIにコードを書かせることでよりスピーディーにマニュアル化を進められるようになっていき、さらにeラーニングのシステム構築にもつながりました。マニュアルをベースにQ&Aを生成することで、職員が場所を選ばず、自発的に学べるようになっていったのです。
-
岩下 順一さん
-
以前から自院でSEを採用し、ICTに長けた職員が積極的に関わってくれたことも大きかったかもしれませんね。もともと西崎院長は新しいものが好きで、恐れず取り入れていくタイプ。患者さんにより分かりやすい経過説明などを行うため、時代に先駆けて、当院では1988年からコンピュータが導入されていたほどです。また、何か新しい提案をした時、否定から入るのではなく「やってみよう」という姿勢で応えてもらえるので、職員にもそうした文化が根付いていったのではないでしょうか。
-
西崎 哲一先生
-
今回、マニュアル作成に取り組んだことで、職員の意識改革にもつながったように思います。業務を具体的にかみ砕いて理解するプロセスを経て、各人の技術や思考のレベルが向上し、「漠然と考える」ことが減った印象ですね。また、橋本顧問に介入してもらったことで、個人的にも知見が広がっていきました。自院で診療に当たる時間が長いクリニックの医師は、どうしても外部との交流が少なくなりがちです。世の中の流れに付いていき、最新情報をしっかりとキャッチアップするには、外部顧問に関わってもらうことが有用だと感じました。例えば、診療記録の作成などにAIを生かす試みについても、橋本顧問のアドバイスがあってこそ着手できたことで、今後ますます注力していくつもりです。
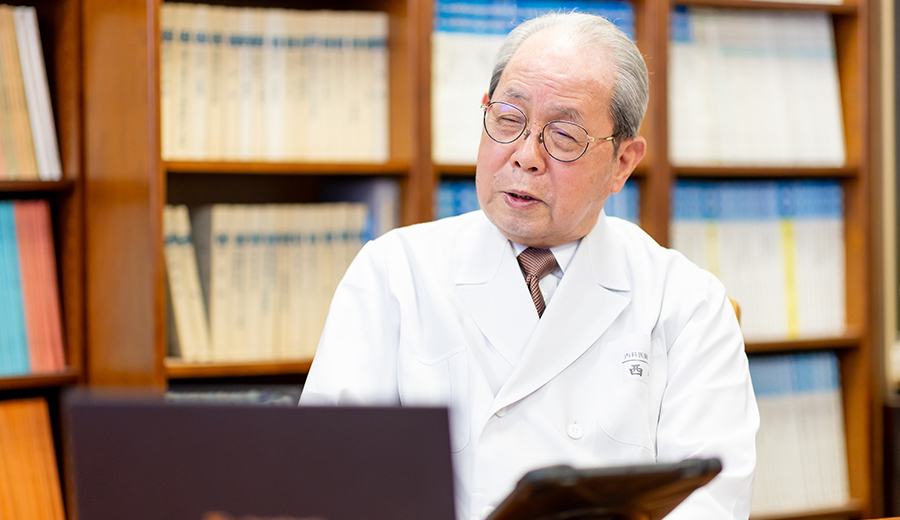
自院にマッチしたオリジナルの人事評価制度とは?
-
橋本 Bob宏昭さん(医療・介護経営の専門家)
-
もう一つ、マニュアル作成と同時並行で動いているのが、人事評価制度の確立です。これまで国内外の一流企業でも多数、人事評価制度に携わってきた経験を踏まえ、現場の意見や実情もお伺いした上で、同院オリジナルの制度を提案しました。こうした制度は「既製品」をそのまま導入しても、実態に則していなければ活用が見込めません。現場と外部の専門家が手を取り合い、共につくり上げていく姿勢が大切なのだと思います。
-
岩下 順一さん
-
西崎院長や事務長である私はもちろん、職員への聴き取りも重ねて、当院に必要な項目へと一つずつ落とし込んでもらいました。他院には適用できない、完全オーダーメイドの人事評価制度ですね。「〇〇を達成したら、次は〇〇に取り組む」といったことが見える化される中で、客観的かつ公平な評価が可能になりました。マニュアルと連動させることが非常に重要で、業務を標準化し、それと矛盾が生じないかたちで人事評価制度もつくり上げていくことに意義を感じます。

-
西崎 哲一先生
-
私は当初、橋本顧問やマイナビの担当者には「うちに大型トラックのような制度はいらないですよ」と伝えました。組織のサイズ感に合わない大がかりな仕組みを提案されても、小道に入った大型トラックの身動きが取れなくなるように、うまく機能しないことが明らかだからです。そうした意味で、橋本顧問は当院の状況やニーズを非常にうまくくみ取って、ぴったりフィットするような提案をしてくれました。
-
橋本 Bob宏昭さん(医療・介護経営の専門家)
-
西崎内科医院の素晴らしいところは、こうした院内改革に、すべての職員さんが真剣に取り組んでくれること。西崎院長にも岩下事務長にも発信力があり、私が伝えたことが、しっかりと全員に行き渡るのです。また、経営数値を包み隠さず共有いただきながら前進できたこともポイントでした。医療機関であっても、継続的に組織を成り立たせるには適正な収支管理が欠かせません。西崎内科医院はキャッシュフローなどの数字が良好で、職員の賞与や新たな医療機器の購入など「必要なところにしっかりと投資する」という感覚にも優れています。こうしたベースがあるからこそ、制度面の改革も順調に進んでいるのではないでしょうか。
「ワンチーム」の魅力を次世代へつなぐために
-
西崎 哲一先生
-
「チーム医療が大切」とはよく言われることですが、その中心に置くべきなのは、やはり患者さんです。つらい症状に悩む方の苦しみを和らげたり、よりよい生活をサポートしたりするためには、診療に携わる職員が心豊かで、ゆったりとした気持ちで業務に当たることが欠かせません。長い人生では楽しいことばかり起こるわけではなく、悩み事のない人間などいないでしょう。だからこそ「ここに来ると気持ちが和らぎ、落ち着いて働ける」という職場環境を構築することが、医療関係の経営者には求められるのだと思います。一つの家族、一つのチームという感覚は、やはり重要ですね。
-
岩下 順一さん
-
こうして西崎院長がつくり上げてきた「チーム西崎」に、橋本顧問もばっちり溶け込んでいますよね。いつも啓発的なメッセージを頂いて、訪問時に会えないと職員たちが寂しがるほど。日々のやり取りからも、当院への愛を感じます。また、新規性のある提案も大きな魅力です。例えば、先日はポッドキャストの機能を活用した音声配信について教えてもらいました。看護師の申し送り、職員への情報共有、院長から患者さんに向けた発信など、さまざまな場面でコミュニケーションツールになっていきそうです。

-
西崎 哲一先生
-
「相手の話を聴く」「分かりやすく伝える」ことが、橋本顧問は上手ですよね。紛れもない特技だし、こうしたコミュニケーションの姿勢や技術を生で感じられることが、私自身の診療にも生かされていると思います。
-
橋本 Bob宏昭さん(医療・介護経営の専門家)
-
ありがとうございます。西崎内科医院は地域から本当に愛されている医療機関で、「最期まで西崎先生に診てほしい」という方も多いそうですね。患者さん一人ひとりの声に耳を傾け、大切に向き合い続けてきた結果でしょう。こうした西崎院長の思いや同院ならではの魅力はそのままに、制度面を盤石にするお手伝いができるのなら、これに勝る喜びはありません。
-
西崎 哲一先生
-
私は今年で86歳になりました。生涯現役でいたいという思いがある一方で、経営という側面では次世代の引き継ぎを考える年齢です。時代の流れによって求められる機能が変化したり、世代交代により専門領域が変わったりしても、地域の皆さんのために貢献し続けることが目標。医療機関の経営者としての責務を果たすために、さまざまなことに柔軟に挑戦できる人間でいたいと思います。

【医療法人社団 西崎内科医院(岡山県倉敷市)】
1977年に開院、2001年2月に新倉敷駅近くに新築移転。一般内科の外来診療を行い、必要に応じて入院治療も可能(19床)。また、多数の透析ベッド(64床)を備え、慢性腎不全の患者さんに対して充実したケアを提供している(夜間透析も実施)。
法人情報
data

- 法人名
- 医療法人社団 西崎内科医院
- 業種
- 医療
- 規模
- ~ 19床
- 支援期間
- 6カ月
- 支援テーマ



